
|
|
�u�w�����܂����v�B�₤Amazon�� �C�G�X�ƉC�u������ |

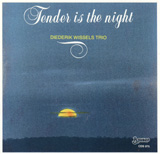 ���������� |
Diederik Wissels Trio "Tender is the Night" (B-Sharp : CDS 075) �@niubi �Azephir �Bwhy not? �Cpandora �Dce que je pense que tu penses que je pense �Etender is the night �Flisten to the loon �Gwhere were you? �Hta matete �Iepitaphe pour la Belgique Diederik Wissels (p) Philippe Aerts (b) Jan De Haas (ds) �������_���u�����b�Z���ɒu���Ă邹�����C�]���ł̓x���M�[�n�̈�ۂ������f�B�[�f���b�N�E�E�B�b�Z���Y�́C1960�N���b�e���_�����܂�̃I�����_�l�B�x���M�[�ɂ�8�̍��ڏZ���C1978�N�ɂ̓o�[�N���[���y�@�֗��w�B�P�j�[�E�h�����[�ƃW�����E���C�X�Ɏt���B1984�N�̑��ƌ�̓W���[�w����`�F�b�g��n���g�̘e���ł߂ē��p��\���܂����B�ނ͉̎�̃f���B�b�h�E�����N�X�Ƃ̑o���R���{�������̒��S�ɐ����Ă���C1994�N�ɂ́w�n�C���b�N�E�\���O�X�g���X�x�Ń������h���̍ō��܁iCHOC�j���l���B1999�N�ɂ́w�o���_���J�[�x�ŋ��̃W�����S�܂Ƀm�~�l�[�g����C2006�N�ɂ͓��܂���܂��܂����B�����̃C���@���E�p�f���A�[���ɒʂ��鏖����C�ނ̃s�A�j�Y���̑傫�Ȗ��́B��ȃZ���X�����ɗD�ꂽ�Ƃ�����ǂ����Ă���C���̌��M�́C1998�N�Ƀx���M�[���c�������瑡��ꂽ�N�ԍŗD�G��ȉƏ܂ŏؖ��ς݁B���ꂾ���ɁC�p�f���A�[���Ƃ̗B��̈Ⴂ���g���I�^���ɂ܂邫�苻�����Ȃ��_�E�E�Ƃ����̂͊u�C�~�y�Ƃ��������Ƃ������B�f�r���[�Ղɂ�����{1990�N�Ղ��C���̌�̘^�����䂦�ɓˏo�������݊��������Ă��܂����̂��C�d���Ȃ��Ƃ����܂��傤�B�K�^�������̂́C���̗B��̃g���I�삪�C��ύD���e�Ȃ��Ƃł����B��������͒��x�C�p�f���A�[���̏G��w�N���[���E�I�u�X�L���[���x�Ɨǂ����Ă���B�Ȃɂ���Ă͎�C�t���[�Y���܂Ƃ߂���Ȃ��������U������C�Ⴓ�͟��ނ��C�S�Ȏ��삵���y�Ȃ̔������ƁC�m���ȋZ�I�C�����E�f�E�n�[�X�̃V���[�v�ȃV���o�����j�ɂ�������ǐ����郊�Y�����ƁC�����Ƃ��낪�����Ă���B���[�x�����}�C�i�[�Ȃ������C�S���Ĕ��̌����݂Ȃ��B�g���I����܂�ō���Ă���Ȃ��l�Ȃ̂ŁC�{�Ղ͓�d�O�d�ɋM�d�ł��傤�B�ǂ����Ō����čĔ����Ă���Ȃ�����ł��傤���B�V�삳����C�ʖڂł����H |
![]()
| Recommends |
 Arthur Honegger "Les Mélodies" (Timpani : 1C1140) Arthur Honegger "Les Mélodies" (Timpani : 1C1140)Brigitte Balleys (msp) Jean-François Gardeil (btn) Billy Eidi (p) �I�l�Q���̉̋Ȃ͑傫���Q�̎����ɕ�����Ă���C�����1920�N�Ɋ|����܂ł̂S�N�قǂɏW���B�����1940�N��ɓ����Ă���ۂ�ۂ�Ə����ꂽ�ӔN�̍�i�Q�ł��B������i�w�S�̉́x��w�|�[���E�t�H���̂R�̎��x�C�w�����鎩�R�x�C�w�A�|���l�[���̂R�̎��x�Ȃǂ́C�ǂ�������Ă��܂�܂�h�r���b�V�X�g�B���������Ύ��Ȃ����m���Ȃ܂ܓ��ۂ���N�̏K��Ȃ�ł��傤����ǁC�V���̃I�l�Q�������ɁC����ł��[��������قǂ��܂ɂȂ��Ă���B����ȉ��߂������Ȃ�������l�������Ƃ́B�h�r���V�[�������̔ނ��R�N�g�[�̂����ł��炮��h�炬�i�w�U�̃|�G�W�[�x�j�C�w�T���^���X�x�ł͐[�����T�Ǝv���̐��E�ɍ~��Ă���B�l�ԃI�l�Q���̐��^�ʖڂ����邪�䂦�̐Ƃ����C�F�Z�����e���ꂽ�̋ȏW�ł͂Ȃ��ł��傤���B�̋ȏW�����ɁC���W�������ɔ�ȑz�͋����قǃ����f�B�A�X�ŊÂ��B�S�W�������܂߂āC�ł������₷�����ނɓ���C�ł����荞�݂₷��CD�ɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B���t����́C�}���^���̉������L���ɐV�����u���W�b�g�E�o���[�Y���j�ƁC���������̉̋ȏW�������������K���f�[������B�s�A�m�͘V���đ听�����r���[�E�G�C�f�B�B�K���f������̂�������ʂ�Ȃ��̂́C���q�����ЂƂ������̂��B�������C�^�����܂߂Ă���ȊO�͑�σ��x���������Ǝv���܂��B���Ƀo���[�Y����͂������̏�肳�Ŋ������܂����B�I�l�Q���̓��g�傪�l�܂������E�Ղł������܂��B���������� |
 "Prélude, Récitatif et Variations (Duruflé) Romanesque
/ L'Enchanteur / Portraits de Peintres / Danse pour une Déesse (Hahn)
Trio (Weinberg) Trio (Nikolayeva)" (BIS : CD-1439) "Prélude, Récitatif et Variations (Duruflé) Romanesque
/ L'Enchanteur / Portraits de Peintres / Danse pour une Déesse (Hahn)
Trio (Weinberg) Trio (Nikolayeva)" (BIS : CD-1439)Sharon Bezaly (fl) Ronald Brautigam (p) Nobuko Imai (vla) ���ϑ��I�ȕҐ��̂��߂��C�^���̏��Ȃ��f�����t���̉B�ꂽ���i�w�O�t�C�N���ƕϑt�x�ŁC�悤�₭���E����ɒl���鍂�����̘^�����B2003�N�ɁC�J���k�E�N���V�J���E�A���[�h�̍ŗD�G�V�l�܂��l��������̎��t���[�g�������C�啨������������Ղł��B�s�A�m�̃u���E�e�B�K���́C�R�b�z����o���h�r���b�V�[�W�̊ۂ��ϐ��̎�ꂽ�Ō�����ۂɎc�閼��B�{�Ղł��\�z�ʂ�C���ɕ\��̐������������Ō��ŏ�����x���B�{�Ղɉ��삷��D�܂�������́C�ނ̋ϐ��̎�ꂽ�s�A�m�Ɉ˂�Ƃ��낪��ł��傤�B�t���[�g�̃V����������͓����܂��L�����A�̐V�l����Ȃ���C�p�����y�@�Ńt���[�g�Ǝ����y�ꓙ���l�����͈̂ɒB���Ⴒ����B���l�̂���ɔ�����d�����F�Ȃ���C���肵���Z�ʂŁC�啨�ɕ����Ȃ��D�����I���Ă���Ǝv���܂��B�ɂ��ނ炭�́C���̕ςȕҐ��Ń��p�[�g���ɍ������̂ł��傤�B���^���l�܂�Ȃ����ƁB���^�̃A�[���͒x��Ă����ʑ����}���e�B�X�g�B���ς�炸�v���M���́u�ljƂ̎q���v�Ԃ�𖡂킦�镽���ȋȑz�Ȃ���C���������ۂ͂Ȃ��B���^�̃��C���o�[�O�͂����ɂ��|�[�����h�̃��_���l�炵���C�s���ɗh��������̓��[�Z�����疳����`�����L�т鉄������Ɉʒu�B�j�R���C�G��������ӊO�Ȃقlj����ȃ��}���h���@�B��������Ȃ͒����������̈���o�܂���ł����B���������� |
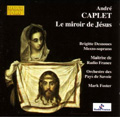 André Caplet "Le Miroir de Jésus" (Marco Polo :
8.225043) André Caplet "Le Miroir de Jésus" (Marco Polo :
8.225043)Mark Foster (cond) Brigitte Desnoues (msp) Maîtrise de radio France : Orchestre des Pays de Savoie ����͂��炵���B�ǂ��ɂ����`�������肷���тł���Ă�B�����[�x���̃C���[�W�@�ł��Ȃ��}���R�E�|�[���ɂ��Ă͒������C�l�I�Ɉ�����������B�J�v���_���`�̌���������ɍČ��O�����D�^���ł��傤�B�̏��S���̃u���W�b�g�E�f�k�G�́C�����}���R����o�Ă���\���{���k�ǂ̃��[�}��܉����I�ł�����Ɖ��̂���������I���Ĉ�ۂ��c���������B�m���x�͂ς��Ƃ��܂��ǁC������ӂ̈ꗬ�̎�͌y�X�R�U�炷�����ŁC�R���g���[������肢�B�{�Ղł͎句��S�����C���̋Z�ʂ�������Ȃ��������Ă���B1987�N�̃N�����������t�F�����ۉ̏��R���N�[���̗D���҂Ƃ͐\���C���ۓI�Ȏ�ܗ��͂��܂茩�����炸�C���ە���֗����ɂ����l�q���Ȃ��B���ꂾ����肢�̂ɖܑ̂Ȃ��ł��˂��B�e���ł߂镧���c���������c���C�������������N�ւ�������������̂́C�A�[�e�B�L�����[�V�����͗ǂ������C���������������c�ƌ݊p�ȏ�̏��������Ă���B�܂����}���R�������܂ł���CD������Ă���Ƃ͎v�킸�C2009�N�܂Ŕ��킸�ɂ����s����p���܂����B���ꂾ���ɗB��c�O�Ȃ̂́C�̏��w�̎��ɔ䂵�āC�����ɂ��i�����Ȍ��̊y�c���B���y�A���T���u���炵���T���H���B���ǃ����o�[�̔ނ�́C�Ȃ�قǒn���I�P�Ƃ��Ă͑����ɗǂ��P������C���Ȃ�̌����B�������Ȃ���C�ǂ����Ă���������ł͉��F�ɎG�݂�������C�Z�ʕs�������炿��`���Ă��܂��܂��B�B�̖`���ɏo�Ă���X���[���Ȃ���̑����A���y�W�I���ǂ���B���œ���͕̂�����܂����ǁC�����ł����A�g�ɗ��ꂪ�����C����C���ɖ��Ă��܂��̂́C�n���I�P�̔߂������E�ł��傤�B�������������Ă��C���̐����Ȃ�[���ɂ����^���B�������ǔł������Ƃ��́C�[�����̑�����ʂ����Ǝv���܂��B���������� |
 Georges Auric "Phèdre / Le Peintre et Son Modèle"
(Timpani : 1C1090) Georges Auric "Phèdre / Le Peintre et Son Modèle"
(Timpani : 1C1090)Arturo Tamayo (cond) Orchestre Philharmonique de Luxembourg �Z�l�g�ň�Ԕn�����ۂ��C�l����������Y���ƃI�[�P�X�g���[�V�����Œ���������Ɋ��������B���ꂪ�I�[���b�N�ł��B�����ɋY��I�ȃ~���[�ł���C��N�͐[������Ƃ����₩�ȓc�ɏ���Ƃ肢�ꂽ�̂ɁC�I�[���b�N�Ƃ�����n���܂�������B�̋ȂȂ�ĉ��i�̋ɂ݂ŁC�^�ʖڂɊϏ܂��悤�Ƃ����C���������Ă��܂��E�E�ƁC�����܂ŏ������Ƃ���ŁC�����v�킹�邱�Ƃ������͔ނ̑_�����̂��̂������낤�Ȃƍl���������ɂ͂����Ȃ��̂��C�ނ��������܂Ɋ_�Ԍ�����ˋC�B�����Ȃ��f��^���̍Ĕ��Ղɏ����C�n�B�����I�[�P�X�g���[�V�����̎��|�ɁC���Ȃ���100�N�O�̃p���N���b�J�[���邢�̓��b�p�[�̌��e�����Ă��܂��B�Z�ʂ�����Ȃ���C�����ăo�J�B�����ɐ����I�Ӑ}���܂C�v�f�����Ղ�̓����t���������Ƃ��C�@���ɓ`����ɏ[���ł����B�X�g�����B���X�L�[�̉e���̉��C�O���ƈ����ւ��̖��含�ɁC�����炭�ނ̓N���V�b�N�̖������݂��̂ł��傤�B2005�N�ɏo���{�Ղ́C�I�A�i�̘^���ł�����݃^�}������ƃ��N�Z���u���N�����̃R���r�ɂ��I�[���b�N�̃o���G���y�I�B��s����̋ȏW���ނ̈���ȓ����̋ɂ݂𑨂��C�}���R�|�[������ێ�`�|�p�����������ɏk���R�s�[�����C�肷���ѓI�u�]�|�v��I��ɂ���̂ɔ�ׁC�^�}������͂������C�ނ���u�_�Ԍ�����{�C�̊����N�₩�ɐ����ẴJ�b�v�����O�B�ٖ��Șa���ƃX�g�����B���X�L�[����̃o�[�o���ȃ��Y��������Ȃ��C���X���鏃���y�o���G�B���Ɍ�҂́w��Ƃƃ��f���x�͊nj��̌���C����ȊO��CD�ɂȂ��������͂Ȃ��̂ł́B���ɉ��l����ꖇ�Ƃ����ėǂ��Ǝv���܂��B�^�}������ȉ��̉��t�w�͑��ς�炸�����x�����Ȃ݁B���̃��x���̉��t�ŁC�I�[���b�N�̔��_�ł���B�҂Ȋnj��y�@�����\�ł���{�Ղ́C�ԈႢ�Ȃ��I�[���b�N����Ƃ��čł����E�ߓx�̍����ꖇ�Ɛ\���܂��傤�B���������� |
 Mel Bonis "Suite / Andante et Allegro / Air Vaudois / Septour-Fantaisie
ou Concerto / Scènes de la Forêt / Suite dans le Style Ancien
/ Pièce / Une Flûte Soupire / Scherzo Final" (Hänssler
: CD-No.93.204) Mel Bonis "Suite / Andante et Allegro / Air Vaudois / Septour-Fantaisie
ou Concerto / Scènes de la Forêt / Suite dans le Style Ancien
/ Pièce / Une Flûte Soupire / Scherzo Final" (Hänssler
: CD-No.93.204)Tatjana Ruhland, Christina Singer (fl) Florian Wiek (p) Wolfgang Wipfler (hrn) Lukas Friederich (vln) Ingrid Philippi (vla) Ansgar Schneider (vc) ��ɃP�N�����̃t���[�g�ȏW��^�����Ă��ꂽ�V���g�D�b�g�K���g�̑f�G�Ȃ��o���܃^�`�A�i���j���C���x�͂Ȃ�ƃ������{�j�̃t���[�g�ȏW�𐧍�B�唼�����E���^���ł��B�����`�I�V���g�D�b�g�K���g���y�A�J�f�~�[�̋�������ɂ��ăR���[�j���E�x�[�g�[�x�����ۃR���y�̗D���҂炵���t�����A���E�E�B�[�N�����t���C�K�v�ɉ����ăV���g�D�b�g�K���g�������̃����o�[�������B�{���������u���Ă������蕧�ߑ�̃��b�J�Ɖ����Ă���ނ̒n�́C���ւ̌����̐[�܂��@���Ɏ����Ă���Ɛ\���܂��傤�B�{�j�͏����ł��������䂦�ɋU���ʼn��y�������������C�D���Ȕގ��Ƃ������ł��Ȃ��܂܁C�߉^�̐l���𑗂�H�ڂɂȂ������K�̏�����ȉƁB�N�Ⴂ�u�[�����W�F�Ƃǂ��ƂȂ����܂�����ǁC1858�N���܂�̃{�j�̏��@�͂����ƕێ�I�ŁC�t�����N�剺�̔��ӎ���F�Z�����P�����Ô��������I�Ȃ��̂ł��B����ł��āC������}���h��࣏n�ƃh�r���b�V�[�ւ̓��ۂ��`�����Y���ƂȂ��āC��i�Ȋ��\���������o���Ă���Ƃ��낪�f���炵���B�I�P�̒c�������S�����ɁC�ׂ������Ƃ������Ώ����t���[�g�͑��̉������߂�������������ł����ǁC�����ł߂锺�t�w�̒g���ȃT�|�[�g�ŏ[���t�H���[�ł��Ă���B��s���郔�H�C�X�E�I�u�E�����N�X�̂��̂�蒮���₷���Ȃ������ł����C���t�������Ĉ���������Ă͂��܂���B����̗e�Ղȃw���Y���[���炱��Ȃ��̂��o��Ƃ́B�L������ł��B���������� |
 Charles Koechlin "La Loi de la Jungle / Les Bandar-Log / Berceuse
Phoque / Chanson de Nuit dans la Jungle Chant de Kala Nag / La Méditation
de Purun Bhagat / La Course de Printemps" (Accord : 480 0792) Charles Koechlin "La Loi de la Jungle / Les Bandar-Log / Berceuse
Phoque / Chanson de Nuit dans la Jungle Chant de Kala Nag / La Méditation
de Purun Bhagat / La Course de Printemps" (Accord : 480 0792)Stuart Berdford (cond) Vincent Texier (btn) Jacque Trussel (tnr) Iris Vermillion (msp) Orchestre National de Monpellier Languedoc- Roussillon : Choeur des Opéras de Monpellier �Ƃ��Ƃ��P�b�N���������œg�̐V�^CD���o�鎞��ɂȂ�܂����B�}���R�����I�����̂Ȃ�����15�N�O�̏��l����ƁC�܂������u���̊�������܂��˂��B�I�P�͑S�������B���������Ŏ蕺�Ɏ���W��^�������郋�l�E�P�[�����O���C1990�N���特�y�ēƂ��ċ�������ԁB���炭�͂��̂����ŁC����ȉ��ڂ����I�P�ɂȂ����̂ł��傤�B�ނ̂��A���ǂ����C1999�N�ɂ͍����I�[�P�X�g���ɏ��i����������͗l�ł��B���̃I�P�́C���C�u�^����CD�����ă����[�X����v���W�F�N�g���V���[�Y�����Ă���悤�ŁC�������H���������ƂɃG���U���Ƃ��f���T�p���Ȃ̕ϑԃv���[�����X���Չ��B�{�Ղ��������ɘR�ꂸ�C�w�W�����O���E�u�b�N�x���֘A�������܂Ŋ܂߂āC��Ȏ҂̎w���ʂ�̋ȏ��őS�ȉ��t�E�E�ƁC���S�ɃI�^�����̎d�l�ɂȂ��Ă���B�����K���Ă��N���V�b�N�̌䉉�t��ɑ����^������C�u�ق�`��E�������`��v�݂����ȃP�N�������������ׂ����蒮�����ꂽ���S�Ȃ�ϋq���Z�̐S���C�S��肨�@���\���グ��B���̑����]���̂��A�ʼn�X�P�N�����D���́C��l�R�Ƃ����I�[�P�X�g���[�V�������\�S�Ɋ��\�ł���w�v�[�����E�o�K���ґz�x��w�J�[���E�i�[�O�̉́x���C������t���킦��Ƃ�������ł��B�K�^�ɂ��{�ՁC���t���ǂ��B�^���œ������Ă��镔���͏��Ȃ��炸����悤�ŁC�ו��𒍈ӂ��Ē����ƁC���������ɉ���������������ɂ͂���̂ł����C�K�x�ɋ�����u�����W�������K�����Ă��C�ׂ����e�������������ʂɂ���Ă��Ȃ薀�ŁB�}���R���͂����ƈ��S���Ē����܂��B�ɂ��ނ炭�́C���C�u�䂦�̊P��������⑽�����ȁB�܂��C����͕s�R�͂ł��傤�˂��B���������� |
 Jean Cras "Hymne en l'Honneur d'une Sainte / Panis Angelicus / Messe
/ Ave Verum / Dans la Montagne / Ave Maria / Regina Coeli / Marche Nupitale"
(Timpani : 1C1120) Jean Cras "Hymne en l'Honneur d'une Sainte / Panis Angelicus / Messe
/ Ave Verum / Dans la Montagne / Ave Maria / Regina Coeli / Marche Nupitale"
(Timpani : 1C1120)Pierre Calmelet (cond) Sophie Marin-Degor (sop) Pierre farago, Vincent Rigot (org) Catherine Montier (vln) David Lauer (tnr) Le Madrigal de Paris ��������N���[�X�ۛ��ɂȂ����^���p�j�����̂��у����[�X�����̂́C�S�Ă����E���^���ƂȂ�@����i�W�B�{�Ƃ��R�l����ŁC���܂�@�����y�Ƃ����C���[�W�̕����Ȃ��ނ̍��@���Ȃ́C�m���Ƀt�H����t�����N��̍����I�ȕM�v�ɔ�ׂ�Ƃ����ԏ����I�B����C�̂Ȃ����Ղ�̕���ł��B���������̕��t���o�́C���܂Ōڂ݂��Ȃ������̂��M�����Ȃ��قǍI�݂Ŋ��S���܂����B�w��������J����������̓W���l�[�����y�@���o���̂��C�p���������y��w�w���@�Ȉꓙ���l���B���̌�R���{�̃A�V�X�^���g�ƂȂ�C���[�U���k�����A���T���u���̏����w���҂�����Ă����Ƃ��B����ȔނɌ����߂�ꂽ�̂��C1970�N�Ɍ��c���ꂽ���̃A�}�`���A�����c�B1988�N�ɃJ�����������y�ēɂȂ��Ă���͍����v���͂����̃��x���ɏ㏸�B��1989�N�̃v�[�����N�̏��R���N�[���œ��܂���ƁC�g�D�[�����ۍ����R���N�[���ł�1992�N��1995�N�̓�x�ɓn���ėD���B1993�N�ɂ̓����g�D�[�L�O���ۍ����R���N�[���ŐR�����܂ƒ��O�܂���܂���܂łɂȂ��������ȁB���F�̓A�}�`���A�B���ꗬ�̍������ɔ�ׂ�ƁC�m���ɏ����L���͑e���C�ׂ����p�b�Z�[�W�ɂȂ�Ǝ����͏o���ł����ǁC�f�l�ł��̐����͋��ٓI�Ȃ̂ł́B�������Ƃ��̂����ɏ����Ȃ�������̂́C�o�����ς�̃\�t�B�[�E�}�������h�S�[�����j���R���g���[�������ȉ̏����I���܂��B�[���撣�������Ƃ͔F�߂���ŁC�����Ė������̂˂��肵�܂��ƁC�����������x�̍����A���T���u�����̂�����C���炭�S����������͂������o�����̂ł́C���Ă��Ƃł��傤���B���������� |
 "Sonata in F Major (Debussy) Fantasy in C Major (Fauré) Sonatine
op.30 (Tournier) Pièce in C Major (Chausson) Sonatine en Trio in
F# Minor (Ravel)" (Claves : 50-240S) "Sonata in F Major (Debussy) Fantasy in C Major (Fauré) Sonatine
op.30 (Tournier) Pièce in C Major (Chausson) Sonatine en Trio in
F# Minor (Ravel)" (Claves : 50-240S)Gaby Pas-Van Riet (fl) Gunther Teuffel (vla) Xavier De Maistre (hrp) 2004�N�ɏo���{�Ղ́C�P�N�����ł������肨����݂ɂȂ����쐼�h�C�c�����i�V���g�D�b�g�K���g�j�\���������́C�t�����X���ۃv���W�F�N�g�B�x���M�[�o�g�̃t���[�g�́C�A���g���[�v���y�@���o����C1973�N�Ƀh�C�c��艹�y�܂ƃx���M�[���c�����e�k�[�g�܂���܁B�R���[�j��������o�āC�o�[�[�����y�@�Ń��[�J�X�E�O���t�Ɏt�����C���݂̓V���g�D�b�g�K���g�������̎�ȃt���[�g�����B�����̃��B�I���Ƃ́C�����I�P�̂����ԂŁC�P�b�N�����Ȃ���ł��̂ŁC�{�Ղ̊����C�t�����g�������o�����̂ł��傤�B�������Ƀt���[�g�͒��ꗬ�ǂ���ɔ�ׂ�Ǝ�C���������ł����C���B�I���̓h�C�c�n�炵�����J�N�J�N�ƍd����\�����C�ɂȂ�Ƃ����Ȃ��ł����ǁC���̃t�����g���J���@�[���ė]�肠��̂́C����ς�Ԃ�������̃L�����A�����n�[�v�̃��X�g������B���l���̃E�C�[���E�t�B����Ȃɂ��āC1998�N��USA���ۃn�[�v�E�R���N�[���i�u���[�~���g���j�D���̃L�����A�͈ɒB���Ⴒ����B���̗���ł����₩�ȃn�[�v���C�A�N�̋����̃A�����I�݂ɉ��x���B�g���I�Ƃ��Ă̂܂Ƃ܂�𑊓����x�C���߂���ʂ������炵�Ă���B�����Ƃ����Ώ����B�L�����A�̍������̂܂O�҂̍v���x�ɏo�Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���ꂾ���ɁC�������̂��g�D���j�G�̃\�i�`�k�ӂ�ɂȂ�̂ł��傤�B�����N���x�X�ɂ̓V�����^���E�}�`�E���j�̑f���炵���I�W���B�ʔ������ƂɁC�����ł���͂��̃}�`�E����̂ق���ꡂ��ɂ�������Ɩ��ĂŁC�\�����j���I�B���X�g������̃n�[�v�͏_�炩���C����ł��ĉ^�w�͖����B�ǂ�������ꂼ��f���炵���B���E�Ɋ����鐦�r�̉��t�ŁC�g�D���j�G�̒�����ׂƂ́C���Ƃ����ґ�B���ꂾ���ŏ[���C������t�K����t�ł������܂��B���������� |
 Jacques De La Presle "Sonate pour Violon / Petite Suite / La Jardin Mouillé / Le Rêve du Jeune Faon / Scherzetto / Orientale / Pièce Brève / Chant Triste / Pièce de Concert / Suite en Sol" (Polymnie : POL590 452) Jacques De La Presle "Sonate pour Violon / Petite Suite / La Jardin Mouillé / Le Rêve du Jeune Faon / Scherzetto / Orientale / Pièce Brève / Chant Triste / Pièce de Concert / Suite en Sol" (Polymnie : POL590 452)Detroit-Windsor Chamber Ensemble ����͒������B1921�N�̃��[�}���҂ɂ��āC�p�����y�@�����B�T�畧�����ǂ̉��y�f�B���N�^�[�߂��v��������̎����y�ȑI�o��B�ނ̍�i�W���o��̂́C���炭�j�㏉�ł��傤�B�L�����A�Ɖ��₩�����Ȃ��痧������M����Ƃ���C�����̔ނ̉��y�́C�����ȃ��_�j�X�g��n�ōs���M�v�B�M���͖R���������C�n���ɕ�����ߑ��@��t�g���C�ێ�I�Ȍ`�����̘g���ŁC�ɂ߂Đ��^�ʖڂɋߑ�̉ԕق��J������B�ǂ̋Ȃ��Ă��C�Ȃ̌`���͂������ĕێ�I�B19���I���̃h�r���b�V�[�̍���ł��B�p�o����]�����@�\�I�Șa���ŁC�����ɐV����̋�C�ɓ�������Ƃ����ȎҁB���^�ʖڂȏG�˂̌˘f�����Ђ��Ђ��Ɗ������C�����قǂɖj���ɂ݂܂����B���y�@�i�݁C���ꂩ�琢�ɏo�悤�Ƃ������̖��C�v�����������N���̓V�˃h�r���b�V�[�����D�ɏ��C��������ƊE��]�������Ă��܂����B�h�r���b�V�[�����݂������V���E�����̉��C�ނ͊����̖�����ȉƂ����ƂƂ��ɉE���������C�����ɓ��g��̃��_�j�Y����ǂ����߂Ă��������Ƃł��傤�B���t�w�̓f�g���C�g�̎����A���T���u���̒c�������B�������ɂ��ꗬ�ǂ���̂悤�Ȉ��芴�͊��҂ł����C�^����Ԃ��܂߂čC�����̂��Ȃ������I�ȉ��ł����ǁC�Z�ʂ͈ꉞ���肵�Ă���C�Ȃ����ɂ͂���قǑ傫�ȕs���R���͂Ȃ��B�����C����Ȗ����ǂ����{���o����CD�ꖇ��낤�Ƃ���S�ӋC�����Ő��E�ɒl���܂��B�f�g���C�g�Ƃ����C�p���[�̍�i�W���f�g���C�g�ł����ˁB�����ɋƊE�l�̃l�b�g���[�N�����Â��Ă��ł��傤���B���������� |
 Heitor Villa-Lobos "Symphony No.7 / Sinfonietta No.1" (Cpo :
999 713-2) Heitor Villa-Lobos "Symphony No.7 / Sinfonietta No.1" (Cpo :
999 713-2)Carl St.Clair (cond) Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR 1998�N�ɘ^������C2000�N�Ƀ����[�X���ꂽ�{�ՂŃ^�N�g��U��Z���g�N���A�́C���傤�ǘ^���̔N�C�V���g�D�b�g�K���g�����ǂ̋q���w���҂ɏA�C��������B�ŏ��ɐ��߂��傫�ȃv���W�F�N�g�����̃��B�������{�X�����Ȃ̑S�W�����������ƂɂȂ�܂��B�w�����ȑ�7�ԁx�́C�O�N�ɏ����ꂽ��U�Ԃɑ���1940�N�㒆���̍�B1949�N�ɍ�Ȏ҂������h������U���ď������Ă��܂��B�����ɂ͑喡�ȂƂ�����݂�����Ȏ҂��C���̔N��ɍ����|�����Ă���Ɨl���I�ɂ��k���ɂȂ�C���Y�������ʁB�t�F���[�̌����Ȃ��v�킹��d���ȑΈʖ@�ƁC�ɍʐF�̘a�����o���������ܒ��I�V�ÓT�h���y�B���ɗǂ������Ă��ĉ��Ƃ����т܂����B�߂�����T���Ȃ�C�w��т̉́x��w�o�[�[���̊�сx�ӂ�̃I�l�Q���ł����B�s���Ȓ��ɂ́C�t�F���[��V���[���z�t�̐F�ʊ��o���_�Ԍ�����B���̌n���̕������a�����D���ȕ��ł�����Ȃ苻�������Ē�����Ǝv���܂��B���^�́w�������ȁx���C�ǂ����������͔͓I�ȋ{�앗�[�ÓT���y�Ȃ̂ɔ�ׂ�ƁC�_�D�̍��B���ɓ���g�J��Ƃ����܂��傤�B�����Ȃ�Ǝc�O�Ȃ̂́C���ς�炸�̉��t�w�B�Z���g�N���A�w���쐼�h�C�c�����V���g�D�b�g�K���g�ǂ͂���ς�ו��̃A�[�e�B�L�����[�V�������e�G�ŁC�����I�O�̉f�批�y�̔��t���B�ׂ����X�^�b�J�[�g������ɖ����������Ȃł́C�s�����̗ь�Ԃ��ۉ��Ȃ����삵�āC��������x�������Ă��܂��܂��B���ꂳ���Ȃ���Η]�T�Ō܂��Ȃ�ł����˂��E�E���O�B����ɂ��Ă��ށC����ȂɌ��M�Ȃ̂ɁC�����Ȃ̘^�������Ȃ��̂͂Ȃ��Ȃ�ł��傤���B���������� |
 Arnold Bax "Cello Concerto / Northern Ballad No.3 / Cortège
for Orchestra / Mediterranean / Overture to a Picaresque Comedy" (Chandos
: CHAN 8494) Arnold Bax "Cello Concerto / Northern Ballad No.3 / Cortège
for Orchestra / Mediterranean / Overture to a Picaresque Comedy" (Chandos
: CHAN 8494)Bryden Thomson (cond) Raphael Wallfisch (vc) London Philharmonic Orchestra �X�R�b�g�����h�o�g�Ȃ���C�C�M���X�ߑ�̍�i�Ɏ�̊O���w���[���C�A�[�m���h�⃔�H�[�����E�B���A���X�ȂǑ����̃}�C�i�[��Ƃɍĕ]���̌��Ă��u���C�f���E�g���\���B�ނ��ӔN�Ɏ��g��ł����̂��C�o�b�N�X�̌����ȑS�W�ł����B���ł����n���h���[��u���r���X���o�b�N�X��^������悤�ɂȂ�܂������C�����̓o�b�N�X�̋ȂȂ�Ėő��Ȃ��Ƃł͒����܂���ł����B�܂��Ė{�Ղɕ��^����Ă���悤�ȌQ���Ȃ́C�܂����ɓ͂��@��͂���܂���ł�������C�g���\���͂܂��Ƀo�b�N�X�ĕ]���̓���t�����l���������Ƃ����܂��傤�B�M���h�z�[�����勳���ɂ��āC�V�����h�X���\����`�F���X�g�̈�l�C���t�@�G���E�E�H�[���t�B�b�V�����}�����{�Ղ́C�o�b�N�X�̑n�슈�����s�[�N���}����1930�N��́w�`�F�����t�ȁx�Ɓw�k���̃o���[�h��O�ԁx��M���Ɋnj��y��i���T�э̘^�B�ڋʂƂ������ׂ��R���`�F���g�́C���̃e�B���^�W����ȂǂƓ��l�C�ނ̊nj��y��i�ɉ��X�ɂ��Č������ȂƂ�܂킵�������I�B���i�ɐU�肩�Ԃ�]��C���Y�����d�������Ă��܂���ʂ��B�o�b�N�X�͎����y�̂ق����ɕt���Ă�C�͂��܂�����ǁC���t�Ȃ̒��Ԋy�͂�w�k���̃o���[�h�x�ɂ������p�I�ȃ����V�Y���͂��̐l�Ȃ�ł̖͂��́B���t���g���\���Ղ̒��ł͂��Ȃ肢�����ނ���Ȃ��ł��傤���B���̌㔠�Չ�����C��s���̒��ÔՓX�ɍs���ƃg���\���Ղ̃o���͎̂Ēl�œ������肳��Ă܂��B������E��������̂ɁC�g���\���̃o�b�N�X�͂҂�����B����������ꖇ��Ɏ���Ă݂�̂��ꋻ�ł��B���������� |
 Louis Vierne "Intégrale de L'oeuvre pour Piano" (Arion
: ARN 268747) Louis Vierne "Intégrale de L'oeuvre pour Piano" (Arion
: ARN 268747)Georges Delvallée (piano) �f���v���`�g�D���k�~�[�����烉���O���ւƘA�Ȃ�ߌ���I���K�����_����ߒ��̚���ƂȂ����Ӗڂ̃I���K�j�X�g�C���B�G���k�́C�I���K���Ȃ̘^�������B���W�������͍ŋ߂܂łقƂ�ǖَE����Ă��܂����B��Љ�̐i�W�ōł����b����̂́C���������l�Ȃ̂����m��܂���˂��B1994�N���痂�N�Ɋ|���ĕ������ꂽ���̂��C2007�N�ɂQ in �P�d�l�����ꂽ���̂ł��B�ǂ��ƂȂ�����t�H�[���I�Ȉڒ����o�ł��ƕψڂ��Ă����ȑz���C�I���K�j�X�g�炵���\���͂����x���B���Ɍ���̍�i���������ꖇ�ڂ́C�����F���̉e�����F�Z���\��C�Ȃ��Ȃ�����B�I���K���Ȃɂ����Β�����C�d�ꂵ���C���[�W�Ƃ͈�����悷�韭�������y�ł��B�s�A�m�̃_�����@���[��1937�N�t���~�G���܂�̃I���K�j�X�g�B�G�R�[���E�m���}���ɐi�݁C��Ȗ@�Ƙa���@���A�����E�V�������Ɋw�Ԃ����ۂ��C�I���K�����A���h���E�}���V�����C�}���Z���E�f���v���C�}���[�E�M���[�Ɏt�����Ă������薣�����C�I���K�j�X�g�̓���I���B���݂̓G�R�[���E�m���}�������߂�T��C����I���K�j�X�g�Ƃ��Ċ��Ă��܂��B�ނ̓g�D���k�~�[���̃X�y�V�����X�g�Ƃ��č����ŁC�w�_��̃I���K���x��S�W�����C��ȉƂƂ��ǂ�������O��m����悤�ɂȂ����l���B���̊w���I�Ȏp���́C�ގ��g���^���̈�N�O�܂ŔF�m���Ă����C���ʂ͌����ݐ�ł��������B�G���k�̃s�A�m�Ȃ��@��N�����đS�W���������̓g�ł����炩�ł��傤�B�e�N�j�b�N�͒B�҂ŁC�����p�b�Z�[�W�ɂ����ł��܂��C���ʔ��݂������Ăł��Ȃ̗����\���J�ɓǂ݂Ƃ��Ă������V�ȕ��ǂ݂ɍD���x��B�����ڐ�����߂Ă��܂�����ǁC���Ɍ��ʂ��̗����^���ɂȂ��Ă��܂��B���������� |
 Maurice Ravel "Intégrale de l'oeure pour Piano Seul" (Accord
: 2CD 476 0941) Maurice Ravel "Intégrale de l'oeure pour Piano Seul" (Accord
: 2CD 476 0941)Roger Muraro, Hortense Cartier-Bresson (piano) �t�҂̃��W�F�E�~�����[���́C1959�N���������܂�B�s�A�m�͂��Ȃ�̒��x�Ɗw�ŏC�������炵���C1978�N�C�����ɂ͗����Ȃ��烁�V�A���̉�����C���H���k�E�����I�Ɍ����߂��ăp�����y�@�i�w�B�ޏ��Ɏt�����ăs�A�m�Ȃňꓙ���l����C1981�N�̃��X�g���ۂŗD���C1986�N�ɂ̓`���C�R���ۂł��S�ʓ��܂��������ȁB�{�Ղ�2003�N�ɏo���ނ̃����F���S�W�ŁC�L�����m���Ȃ�o�������͊��ƕ]���ɂȂ�܂����B�������Ȃ���C���łɂ��̎��L�����A�͌��\���������̂ł��˂��B��������������̂ł��傤�B�S�̂ɔނ̃��Y�����͑O�m���C���B�㉹���̑Ō��͏_�炩���Ĕ���Ȃ���C�ו��Ɏ��܃A�����o��悤�ł��B�܂��C���Ȃ�̃��o�[�g�D���B�w�O�t�ȁx��u�I���f�B�[�k�v�̂悤�ɁC���ꂪ���ʓI�ɓ�����������C�u�O�t�ȁv�i�N�[�v�����̕�j�̂悤�ɁC���o�ߑ��C���ɂ��Ȃ��Ă��܂��B����d�˂Ă����Ԃ܂�݂͏o�Ă�悤�ł�����ǁC���������n�����i�ق����C���̐l�̃����F���͖��킢�𑝂���Ȃ����ȂƎv��ꂽ����ł��B�����ĂȂ��Ȃ��ǂ��R���g���[���͂���Ă�����̂́C���f�Ȃ悤�ŁC���������Ȃ��������t�B����̃s�A�j�X�g���L�́u��鉉�t�v�^�C�v�̂��ɁC�o���s�o�����͂����肵�Ă܂�����C��ʐl���܂Ƃ߂Ē������߂̕W���ՂƂ��ĐϋɓI�ɐ�����v�f�͌����đ����Ȃ��B�����̖��Ղ����݂��钆�ŁC�V���ȑS�W�ՂƂ��ē��M����قǂ̖��͂����邩�Ƃ�����ƁC���������B�ނ��Ȃɂ���Ă͂����ƋP���u�Ԃ��܂܂�Ă��邱�Ƃ��[���ɔF�߂C�����I�ȕ]���͂��������S���Ƃ�����Ƃ̃I�}�P�C�Ƃ������Ƃ���ł͂Ȃ��ł��傤���B�������� |
 Ernest Bloch "Shelomo / Voice in the Wilderness / Prayer (from Jewish
Life)" (EBS : ebs6070) Ernest Bloch "Shelomo / Voice in the Wilderness / Prayer (from Jewish
Life)" (EBS : ebs6070)Antoni Wit (cond) Julius Berger (vc) National-Sinfonie-Orchester des Polnischen Rundfunks �����Ƀ`�F���⃔�@�C�I�����t�҂ɂ��^�������Ȃ��Ȃ��u���b�z�B���_���̔߈��̘U�����������ƁC�V���~�b�g�����̎�p�I�ȐF�ʘa�����Ր��ɐG���̂ł��傤�B�܂��ʂ̑I�����������܂����B1989�N�Ƀ|�[�����h�����̊̐���Ő��삳�ꂽ�C�u���b�z�̊nj��y�ƃ`�F���̍��t�ȑS�W��搂������CD�ł��B�\���X�g�̃����E�X�E�x���K�[��1954�N�A�E�O�X�u���N���܂�B�~�����w�����y�@�ŃE�H���^�[�E���C�q�����g�ɁC�����ŃU���c�u���N�ŃA���g�j�I�E�W���j�O���Ɏt���B���̌�n�Ă��ăV���V�i�e�B���y�@�i�݁C���X�g���|�[���B�`�̃}�X�^�[�N���X����u�������Ƃ��������͗l�B���ۓI�ɂ�1979�N�̃j���[���[�N���ۃ`�F���E�R���y�œ��܌o��������悤�ł��B���͉Ǖ��ɂ��ėǂ��m��܂���ł������C���㉹�y�̐��͓I�ȏЉ�҂Ƃ��Ă͌��\�L���Ȃ悤�ł��˂��B�Y��ɐ������s�b�`�ƁC�d�߂̒���̂��鉹�F�͂����ɂ��Ɖ��n�B���������d���L���L�����Ă�̂͋C�ɂȂ���̂́C�Z�ʂ͊m���ł������t�Ƃ��Ǝv���܂��B������݂̂Ȃ��I�P�͂ǂ���獑���J�g���B�`�F�����ǁB������������Ȃ��ɂ͂����������B�^�N�g��U��A���g�[�j�E�E�B�b�g����͍��ۓI�Ȓm���x�͂Ƃ������C�|�[�����h�ł͖��̂���w���ҁB�G�R�[���E�m���}���ɗ��w���ăs�G�[���E�f�����H�[��i�f�B�A�E�u�[�����W�F�Ɏt�������ق��C�N���R�E�̍������y�w�Z�Ńy���f���c�L�ɍ�Ȗ@���K�������Ƃ�����Ƃ��B1971�N�̃J�������E�R���N�[���œ�ʂɂȂ�C���̏����߂č����ł̕]�����m���B���̌ハ���V�����ǂ̉��y�ēɂȂ����ق��C�V���p�����y�A�J�f�~�[����������Ă�悤�ł��B�������� |
 Wolfgang Mozart "Clarinet Quintet K.581 / Horn Quintet K.407 / Oboe
Quartet K.370" (Philips : 422 833-2) Wolfgang Mozart "Clarinet Quintet K.581 / Horn Quintet K.407 / Oboe
Quartet K.370" (Philips : 422 833-2)Academy of St.Martin-in-the-Fields Chamber Ensemble ����̉����ɂ͂����ς胂�e�Ȃ��̂ɁC�_�����Â������ݕ������l���̃x�e���������ɂ́C�Ȃ����E�P���X�������̂������B������N�قǁC�ӂƂ����e�݂Œm�����Ƃ���ƒn�ɂ��Z�܂��̂��k���܂ƁC�����������ɂ����ʂȂ��Ă���܂��i���������C�����ƈ�ڍ��ꂵ���ł��낤�C�Ɓ`���Ă��m�I�Ń`���[�~���O�Ȃ��k����ł��j�B�ړ_�͂��̕��̐l���Ɖ��y�D�����ĂƂ������Ȃ�ł����C���ł�100�������Ă��邨�N�Ȃ̂ɁC�ƂĂ��������Ⴍ�Ƃ��Ă���������C�����呲�Ńs�A�m�o�J���܁B�h�r���b�V�[�̘b��ɂ���Ȃ����Ă��邩�琦���B������l�ł���ꉞ�B�����`�i���j�B�ŁC�قƂ�Ǖ�������o���Ȃ��ޏ��̂��߁C���܂��Ŕ�����CD�𑗂����肵�Ă�킯�ł����C�߂������Ƃɔޏ��͂ǂ������`���S��`�҂Ȃ킯�ł���B���̌�炢�����悤�Ǝv������C�����������[�����Ƃ��Ƃ��傤���Ȃ�����Ȃ��ł����B���܂��ܔ����Ă͑����Ă�̂ł����C����ς蔃��������ɂ͈�x�͎��ɂ���킯�ł��B�ŁC�u�ӂ�E�E����ς�ȁB������h�C�c���y�͑ʖڂ�v�Ƃ��Ċm�F���ĉx�ɓ����Ă����킯�ł��B�����250�~�R�[�i�[�Ƀ��������Ɣ����B�ǁ`�������̂��̒��q���낤�ƁC����������҂������w�����E�E�B�u���o�C�b�I(@_@�G)�v�]�V�Ռ��슴�����B���������ƂɁC���̈��̌������[�����Ƃ����߂Ĕ������Ǝv���Ă��܂����ł͂Ȃ������̃����`�i�Y�j�B�����ȃh�C�c�G�����y�̒��ł��C�����x�͊ԈႢ�Ȃ��ō��������̌y���j�A�}�f�E�X�̏p���Ɍ����Ƃ��Ă��܂����������p�������`���i�Y�j�B�����Ȃ�ƁC�����̔@���ו��̎G�ȃA�J�f�~�[�����̔��t���C�ɂȂ邱�ƋC�ɂȂ邱�ƁB�V���̂��������ƂȂ�C�����ƃ��[���h�N���X���勓�^�����Ă���܂��傤�B�ǂꂪ�����̂��F�ڕ����炸�C�Ƃ肠��������ς�����̔������Ⴄ�n�R���j���̖��͂Ձ`�Ȃ��B���̑I���C�Ԉ���Ă���܂��傤���H�F�l�̂���������B�������� |
| Other Discs |
 Selim Palmgren "Complete Songs for Male Voice Choir Vol.3" (Finlandia
: 3984-25328-2) Selim Palmgren "Complete Songs for Male Voice Choir Vol.3" (Finlandia
: 3984-25328-2)Matti Hyökki (cond) Talla Vocal Ensemble : Helsinki University Chorus ����͒m��Ȃ������B�����Ƀt�����X�ߑ���،i�ɂ��C�����ȃ|�X�g�E���}���h�s�A�j�Y���������t�B�������h�ߑ�̍�ȉƃp�����O�����́C�j�������̂��߂̍�i�W�B��������O�W�B�������������̍w���Ȃ̂͐\���܂ł��������܂���B�ނ̃s�A�m�Ȃ��āC�^����ɕ����Ԃ̂̓O���[�O�̊�B�����Ȃ��������낤�E�E�ƁC����ɖp�c�ȃ|�X�g�E���}���e�B�X�g���C���[�W���Ȃ���q�����܂��ƁC���Ȃ�������̉����������Ăт�����B���̋�C�E�E�ǂ����Œ������悤�ȁE�E�ƎU�X�v�������炵�ăn�^�ƋC�Â����̂��C���l��̂ł����B�t�F���b�`���E�u�]�[�j�̒�q�Ƃ��ėL���Ȕނ́C1921�N�ɂ͓n�Ă��ăC�[�X�g�}���E�J���b�W�ŋ��t�߂����Ƃ�����܂��B�ǂ����ō��l�S�X�y�����C�����C���X�p�C�A���ꂽ�̂����m��܂���B������ɂ���C�s�A�m�Ȃ���i�J�^���O�̖w�ǂ��߂Ă����͂��̔ނ��C�A���o��4�����ɂ��n�鍇���Ȃ������Ă����Ƃ��������ŁC�[�����M�ɒl����ł��傤�B�ނ̍�i�ژ^�̓e���E�g�~�������쒆�炵���C�ډ��唼�̋Ȃ͍�i�ԍ����Ȃ��܂ܕ��u��ԁB�{�Ղɍ̘^���ꂽ34�Ȃ���ȔN���番����܂���̂ŁC��L�͉����̈���o�܂���B�������C���㌤�����i�߂C�k���̃V���p���Ƃ����F�m����Ă��Ȃ��ނ̍�ȉƑ��ɐV������ł�����邩���m��܂���ł��˂��B�̂��̂̓w���V���L��̍����c�ƃ^�b���E�A���T���u���Ȃ�J�E���^�[�e�m�[���̍����c�̍����B��҂͒j���̂����ɏ����ƌ��������悪����炵���C�{�Ղł����̓�������������Ă���܂��B�c�O�Ȃ���o���̃o�����X�͂��܂�ǂ��Ȃ��C�������Ƃ��Ă̐��x�͍��ЂƂɂȂ��Ă��܂��܂�������ǁB�������� |
 Joaquin Turina "Poema en Forma de Canciones / Tres Arias / Canto a
Sevilla / Tres Sonetos / Tríptico / Saeta en Forma de Salve a la
Virgen de la Esperanza / Tres Poemas / Homenaje a Lope de Vega" (Claves
: CD50-602) Joaquin Turina "Poema en Forma de Canciones / Tres Arias / Canto a
Sevilla / Tres Sonetos / Tríptico / Saeta en Forma de Salve a la
Virgen de la Esperanza / Tres Poemas / Homenaje a Lope de Vega" (Claves
: CD50-602)Manuel Cid (tnr) Ricardo Requejo (p) ���͂قƂ�ǂ��p�ՂɂȂ����Ǝv���܂����C�A���ՓX���܂����������������C���s�̏\�����Ńg�D���[�i�̎����y�Ɗnj��y�̘^���������ċ������L��������܂��B������o���Ă����̂��C�����͌��C�������N���x�X�ł����B���R�͗ǂ�������܂������C�N���x�X�͂Ȃ����X�y�C���ߑ�Ɍ䎷�S�B�g�D���[�i�͑S�W�������ɓn���āC����CD������Ă����͂��ł��B1997�N�ɏo���{�Ղ́C�V���[�Y��܍�B���ۓI�ɂ͂قږ����ŁC�������番����Ȃ���̃e�m�[���C�}�j���G���E�V�h���̂��Ă܂��B�ނ͂̂��C�i�N�\�X����o���t�@�����́w�R���l���x�ɂ��Q�����Ă���m�ŁC�}�h���[�h�����_�Ɋ������Ă���͗l�B���N�̂��������̐��͏[������܂��ǁC�R���g���[���͐��m�ł����C��\�����I�݂Ńr���[�h�I�ȊÂ�������B�����C���N�g�ɂ͏��Ă��C���������o��ŗ���C���������Ă���B����A�Ɗ{�ɉ����������Ă��銴���ŁC�����������ЂƂǂ��Ȃ��B���̂��߁C�Z�I�m���ɉ̂����Ȃ��Ă��Ȃ���C�ǂ����{���q�ɕ������Ă��܂��B������Ȃ��ł��˂��E�E�B���ʐ^���������ł͌��\�C���N�̂悤�ł��B�̂͂�������肾������Ȃ��ł��傤���B��Ȏ҂̕M�v�́C�d�x�ɃX�y�C�����K���g�p���C�ǂ����������t�@�����Ɨޓ��I�B���������Ă��t�������R�L���Y���Ă��܂��B�a���ʂł͊m���ɋߑ�Ȃ���C�O�ʂɉ����o����镑�����Y���ƃA�N�Z���g�̓y�L���ɂ���������C���܂蕧�ߑ�炵�����E���͊������܂���B�t�ɂ����C�̋Ȃ͍�Ȏ҂̖�����`�I�Ȍ����ł��F�Z���o���W�������Ƃ����܂��傤�B�������� |
![]()
| Recommends |
 Woody Shaw "Live Volume One" (High Note : HCD 7051) Woody Shaw "Live Volume One" (High Note : HCD 7051)�@love dance �Alight valley �Bwhy �Cstepping stone Woody Shaw (tp, flh) Carter Jefferson (ts, ss) Larry Willis (p) Stafford James (b) Victor Lewis (ds) ���ǂ��܂蕂����ʂ܂ܐ����������E�f�B�E�V���E���C�ꕔ�̍D���҈ȊO�Ɏv�킵���m���x���Ȃ������̂́C�ŋ߂܂ŐⒸ����CD�����荢��Ȃ����p�Ղ������Ƃ����C�ɂ߂đ����I�ȗ��R�ɉ߂��Ȃ������̂ł́B2000�N�ɏo���{�Ղ���ɁC���v�S���̖����\���C�u���勓���̖ڂ��������ƂŁC�蔖������CBS����̃��C�u�����͔���I�ɑw�������Ȃ�C�����ȕ]������y�낪�������B���ǂ��ꂪ�C��\��w�X�e�b�s���E�X�g�[���Y�x�̍Ĕ��ɂ��q��������ł��傤�B�{�Ղ͂�����̑�\��̑O�N�i1977�N�j�ɘ^�����ꂽ��ǕҐ��̃��C�u�B���Ƃ��Ƃ̓E�f�B���g�����������Ӑ}���Ę^���Ă����}�e���A���̈ꕔ�B����Ȍ|�����ł���̂��C�{�Ղ��v���X�����n�C�m�[�g�В��̃W���[�E�t�B�[���Y���C���ăV���E���ݐЂ����~���[�Y�̑n�ݎ҂�����ł��傤�BCD�ꖇ�ɂ�������4�ȁB�������C���t���Ԃ�57���ɒB���钷�ڃ��C�u�B�s�A�m���I�i�[�W�E�A�����E�K���Y�ł͂Ȃ��C�x�[�X���N�����g�E�q���[�X�g���ł͂Ȃ����Ƃ������C�������Ă��鉹�́w�X�e�b�s���E�X�g�[���Y�x�ƍ��������{���̃��[�h�E�W���Y�B���Ղɍ��ꍞ���ł���C��a���͂قƂ�ǖ����ł��傤�B���ڂȕ��C���x�͏��������܂�����ǁC���L�ѐL�тƉ��t����C�����������g��d�l�́w�X�e�b�s���E�X�g�[���Y�x�B�蕺�����点���N�C���e�b�g�Ґ��ŁC���̏�肫����1970�N��㔼�^���̃��C�u���̂��B���e�I�ɂ��G��ŁC�悭���^���Ă���܂����Ǝ�����킹�����ł��B�n�C�m�[�g����͂��̌�C��S���܂Ŗ����\���C�u���o�܂������C�{�Ղ͑��X�ɔp�ՁB�R���܂ł͂قړ������̘^���ŁC��������ʏo���Ȃ̂ŁC�p�ՂɂȂ�ʂ����ɗ}���Ă����Ɨǂ��ł��傤�B���������� |
 Massimo Moriconi, Dado Moroni, Stefano Bagnoli "Heart of the Swing"
(Music Center : MPJ 1000CD) Massimo Moriconi, Dado Moroni, Stefano Bagnoli "Heart of the Swing"
(Music Center : MPJ 1000CD)�@just in time �Amedley: sunset end the mocking berd - come sunday - do nothin' til you hear from me �Bno greater love �Cold folks �Dwhen the saint go marchin' in �Ea passeggio nel cielo �Fantrophology �GBarbados �Hwhen the saint go marchin' in Dado Moroni (p) Massimo Moriconi (b) Stefano Bagnoli (ds) ����W���Y�̓�咪���Ƃ������[�h�ƃo�b�v�B�e�X�����������Ⴆ�C�������s�A�j�X�g�́C�����������Ɏ��߂Ǝ��̒������{���āC�����F���o���Ă����K�v�ɔ�����B�ȒP�Ȃ悤�ŁC���ꂪ�Ȃ��Ȃ�����B�꒮�L���������݂̂Ȃ炸�C���̃L�����������ƂȂ�C�����͂Ɩ��͂����Ƃ���܂ōs���l�͂Ȃ��Ȃ�����܂���B�C�^���A�̂₭���ȋ����C�_�h�E�����j�́C���̃o�����X���o����ϒB�҂ȃs�A�m�e���̈�l�ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B������͂����܂ŃI�[�\�h�b�N�X�ȃo�b�v�E�X�^�C���B�E�C���g���E�P���[��{�r�[�E�e�B�����Y��C��������̃o�b�v�E�s�A�m�𐳂����p���B����ł��āC����̈��Ăɂ̓}�b�R�C�E�^�C�i�[�̖��I�݂ɗ������C�S���S�������I�ɒe���܂���B���q�̏o�Ȃ��Ƃ��́C��҂������͂��ɕ��邱�Ƃ������ł����ǁC��[���ɏ������X�S�C��ł���ԁB�肪�t�����܂���B1995�N�̃~���m�ŁC�Z�t�ƃX�^�W�I�o�c�҂͓���l���̖{�ՁB���炭���Ȃ�C�y�ɘ^������Ȃ��ł��傤���B�y�����I�ȑ喡���������ۂƁC�h�X�̗������x�[�V�X�g�̊�G����ǂ������B���n���B���[�h���ڂ̂�����d���̂��A�ŁC�ނ������b�N�X���ċ��ɏ��܂����B�Ƃɂ������{�ՁC���ǂ��r������������t���C���ɂ̂т̂т��Ă��đf���炵���B�Ȃ��Ȃ��ŋ߁C���������₴���ꂽ�X�^�W�I�^���͂Ȃ��ł��B�B��C�ɓ���Ȃ��̂́C�ȑO�w�������X�e�t�@�m�E�o�j���[���́w�A�E�W���Y�E�X�g�[���[�x�ƁC�O�Ȃ��܂�܂����Ă��邱�Ƃł����C���̏o���f����O�ɂ���C����Ȃ͍̂��ׂȂ��Ƃł��傤�B������R�Ȓ��̂P�ȇ@�ɒ�����₭���ȃ��[�_���E�o�b�v�Ԃ�C�u���[�W�[�ȃE�C���g���E�P���[�߂����\�ł���B�ȂǁC���x�����Ă����Ƃ�����ł��܂��܂��B���������� |
 Bernie Senensky "Rhapsody" (Timeless : CD SJP 434) Bernie Senensky "Rhapsody" (Timeless : CD SJP 434)�@I hear a rhapsody �Acome rain or come shine �Bgoodbye, Mr.Evans �Cwinnibop �Dtogether �EWinnie's revenge �Fyesterday's thoughts �Gsomeday my prince will come �Hcome rain or come shine (alt.) Bernie Senensky (p) Jim Vivian (b) Bob Moses (ds) ���[�_�[��1944�N12��31���E�B�j�y�O���܂�B�N�����E�p�[���}���ɏA����9����s�A�m���w�сC17����̓{�u�E�A�[�����h�\���ɃW���Y�E�s�A�m���t���B1962�N����1966�N�ɂ����Ēn����G�h�����g�������_�ɉ��t�����������̂��C1968�N����g�����g�ɈڏZ�B�č�����̋q���z�[���t�҂Ɛ������荇�킹�����܂����B ���{�ł͂قƂ�ǖ����ł�����ǁC�J�i�_�ł͂��Ȃ��]�̂���l���炵���C�ߋ��W���m�[�܂ɎO�x�m�~�l�[�g�B�W���Y�E���|�[�g�E�A���[�h�œ�x�ŗD�G�s�A�j�X�g�Ƀm�~�l�[�g���ꂽ�ق��C����́w�N���t�H�[�h�̉́x�Ń\�[�J����ȏ܂���܂��Ă邻���ȁB�A���o�������ł�12���𐔂��C�����[�_�[���1975�N�B�{�Ղ�1993�N�̘^���ŁC���[�_�[�Ƃ��Ă�9���ڂɂ�����܂��B�����[�_�[�ՂŁC�G���@���X�Ƃ̋������̒����}�[�e�B�E���������N�p����ӂ肩����M����悤�ɁC�ގ��g�̓G���@���X�̉e�������F���Ă���C�{�Ղł������I�ȇB���܂އ@��A�C�G�̓G���@���X�ւ̃g���r���[�g���ӎ����Ă̘̍^�Ƃ��B�Ȃ�قǍ���̘a����R�[�h�ł��̓��@�[�����ȍ~�̃G���@���X���B�P�j�[�E�o�����ƃV�_�[�E�E�H���g���������ĎO�Ŋ������悤�ȁC�p���p���������r�C�ʂ̃��[�h�E�s�A�m��e���B�ŋ߂ł��ƁC�}���R�E�f�b�g�ȂɎ��Ă邩������Ȃ��B���܃~�X�^�b�`������C�����ĕ��͂��ꂽ�Z�I�h�ł͂Ȃ����̂́C�t���[�Y�͗ǂ��̂��܂����C�J���b�ƋC�����̗ǂ��X�^�C���ɂ͌������Ȃ��C���芴���Q�B����Ȃ̕M�͂�A�����W�����g���B�҂ŁC�����Ȃ��B���E���W�ƃi�C�g�N���u�Œ@���グ���S�V��^�̃s�A�j�Y���̂Ȃ���킴�ł��傤�B�n���ݏZ�҂̘^���Ƃ��Ă͏\��������قǂ����o�����Ǝv���܂��B�ނ̘^���͑������p�Ղ̂悤�ł����C�����[�_�[����܂߁C��O���͍�������\�Ȗ͗l�B���̂�������Ǝ����Ă݂܂����˂��B���������� |
 Don Rendell Jazz Six "Playtime" (Vocalion : CDLK 4284) Don Rendell Jazz Six "Playtime" (Vocalion : CDLK 4284)�@hit the road to dreamland �Apacket of the blues �Bmy friend Tom �Cit's playtime �Dtickletoe �Ethe lady is a tramp �FDolly mixture �Gthis can't be love �Hby-pass �IJohnny come lately �Jjump for Jeff �Ktres gai �Lthe minutes �Mfounder member �Nboard meeting Don Rendell (ts) Eddie Courtley (tp) Eddie Harvey (tb, p) Ronnie Ross (as, bs) Peter Blannin (b) Andy White (ds) 1926�N�v���}�X���܂�̃h���E�����f���́C15�˂Ŏn�߂��A���g���o�ăe�i�[�ɓ]���B�R�y���̂̂��C1950�N�ɃW���j�[�E�_���N���[�X���d�t�c�ɉ����B1953�N�Ƀ��[�_�[���y�c�֍ĕ҂���ۂɒE�ނ��C���N���玩���̃O���[�v�𗦂��Ċ������J�n���܂����B�ނ́C1963�N�ɃW���Y��]�ƂƂ��Ă��m����C�A���E�J�[���}���č���������f�����J�[�d�t�c���L���B1969�N�ɃJ�[���J���^�x���[�E���b�N�ɖڊo�߂ĉ��U����܂ł̐��N�ԂɁC�p���W���Y�̍��x���������x����d�v����c���Ă��܂��B�����f���Ƃ����C�����O�ɍĔ����ꂽ�����[�_�[�����w�~�[�g�E�h���E�����f���x������܂����˂��B�{�Ղ͂���ɑ���1950�N�����̘^���B�C�A���E�J�[�ƍ��ӂɂȂ�O�̂قƂ�ǂ��C���ǂ��t�����g�ʼn߂������o���g�������C���j�[�E���X��Ƃ̎O�ǃZ�N�X�e�b�g�ŁC���C�ݕ��̃T���T�������W���Y�����t���Ă��܂��B�����f���̃e�i�[�͈꒮�C���X�^�[�E�����O�̗�������݁C�����������F�����ւ��ă��b�`�[�E�J�~���[�J���B�W���ȃt���[�W���O�ŗ��݂Ȃ�搂��C���C�݂�͂ɂ������߂̃A�����W�B�قƂ�Lj�a���������C�݃W���Y�Ƃ��Ē�����B�������������肢��ł����ǁC�l�I�ɂ͂�͂�o���g���̃��j�[�E���X�̃\���Ɋ��S������B�O���v������ł����C���̐l��肢�ł��˂��B���������]������Ă�������Ȃ����Ǝv���܂����ǂ��ł��傤�H���������� |
 Greg Howe "Uncertain Terms" (Shrapnel : SH-1075 2) Greg Howe "Uncertain Terms" (Shrapnel : SH-1075 2)�@faulty outlet �A5 mile limit �Brun with it* �Cbusiness conduct �Dpublic and private �Esong for Rachelle �Fstringed sanity �Gsolid state �Hsecond thought Greg Howe (guitar, all instrumental) Lee Wertman (g-synth)* ���e���M�^���X�g�̑������I���݂̈�l�Ƃ��āC���^���D���̐l�łȂ��Ƃ����O���炢�͒m���Ă���C���O�E�F�C�E�}�����X�e�B�[���B�ނ@�����}�C�N�E���@�[�j�[�̑n�݂������[�x�����V�����v�l���E���R�[�h�ł����BMr.Big�ŗL���ɂȂ����|�[���E�M���o�[�g�C���K�f�X�̃}�[�e�B�E�t���[�h�}���C���J�R�t�H�j�[�̃W�F�C�\���E�x�b�J�[��@�����ނ̃��[�x���́C���Ȃ��瑬�e���M�^���X�g�̌Ղ̌��B�������琶�܂ꂽ�X�^�[�I��̒��ł��C�ЂƂ���ٍʂ���̂����̐l�ł��傤�B�{�Ղ̓\����O��ŁC1994�N�����[�X�B�O�����W�����̉��C�A�i�N���ɉ߂���Â������b�N�E�t���[�W����������Ă܂��B�C���O�E�F�C�ƃ��@���E�w�C�����ɓ�������C�A�����E�z�[���Y���[�X��t�����N�E�M�����o���ɂ��X�|�B�����͂����܂Ńn�[�h���b�N�ɒu�����C�W���Y�ƍ��l�t�@���N���I�݂Ƀu�����h�B�ُ�ɔ��ߍ\���̓���g���J�j�J���ȕϔ��q������Ȃ��e���|���B���Y������^�C�����͕|�낵�����m�ŁC�^�b�s���O����g�������K�[�g�͊��炩�B���e���ɂ����������R�ƕ��сC�܂�ŗ���Ȃ��B���������l�炵���t���[�Y��t���S�����قǃO���[������̂����炽�܂�܂���B���̐l�͍�ȃZ���X���܂������B�{�Ղł��قƂ�ǑS�y�Ȃ���^�B�O���𒆐S�ɗǂ������Ă���B�@�ނ͈����炵���C�X�l�A�h������V���o���ނ̉����r�~���[��������������ł����ǁC����ȍׂ������_�̓|�����Y���Ƙa���̍^���C�����čI������\���̂Ă���ł䂤�䂤�Ƒ��E�B�X�e�B�[���E���@�C�̖���w�p�b�V�����E�A���h�E�E�H�[�t�F�A�x������ɂ��ɂ����C�W���W�[�ȃe�N�j�J���E�t���[�W�����B���y�I�ȕ����������b�N�ł��\��Ȃ���C���Ȃ�ʔ���������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���������� |
 Browne, Haywood, Stevens "King, Dude & Dunce" (New Market
Music) Browne, Haywood, Stevens "King, Dude & Dunce" (New Market
Music)�@s.s.t.t. �Abeach side �Bchange and smile �Csinging the blues �Da boy like that �Esmash up �Frecovery �Gno obligation quote �Hconvert joy Allan Browne (ds) Nick Haywood (b) Tim Stevens (p) �\�N�قǑO�ɁCABC�����̊̐���Ń����[�X���ꂽ�g���I��w�s�ӂ̗z�����ɁiSudden in a Shaft of Sunlight�j�x(1998)���C���N�̍��B���y�Ƌ���y��(�A���A���y��)�Ƀm�~�l�[�g�B�b����ĂI�[�X�g�����A�̎O�l�O�B�Z�ʂ��������Ŕ����̓��^���^�C���Ȃ���ŔN���Ƃ��ă`�[�����������鑾�ۂ̃A�����E�u���E���𒆐S�ɁC�ǂ����������O���[�v�\�����g��̃g���I�ł��B�m���h�̎��e�B���E�X�e�B�[�u���X�̃G���@���X�E���C�N�ȃs�A�j�Y���ƍ�ȃZ���X���C���ł������Ɋׂ邱�ƂȂ��K�x�ɒ��a���Ă������Y�����B�o�������܂��ύt�����o�����X�̗ǂ����g��ŁC������̑���͓��{�ł��b����Ăт܂��������˂��B�{�Ղ͂�����̏o���삩��k�邱�Ɠ�N�C1996�N�ɔ��\���ꂽ�g���I����B���吧��̂��ߎs��ɂ͂Ȃ��Ȃ��o��炸�C���Ȃ蒷�����Ɠ��荢��������E���Ղł��B��{�I�ȕ������͑���Ƃقړ����B����Ŕނ�̃G���@���X�E���C�N�ȐR����`�Ɏ�����������Ȃ�C�قڗ\�蒲�a�I�Ɉ��S���Ă����߂ɂȂ��̂ł́B�Ƃ�����\����ł͑O�q�△���ɐڋ߂��Ă��܂��C�����ł������ɂȂ肪���ȃs�A�m���C�N���̑��ۂ����ǂ��ɂ�ŗ}�����݁C�O���[�v�Ƃ��ẴG���@���X�h�g���I���t�ɐ�O�B�s�A�m�𒆐S�ɃI���W�i�������ς�炸���ɔ���Ŗj�ɂށB�~�������C�o���[�h�s�����ŃR���Z�v�g���m�ȑ���ɔ�ׂ�ƁC�A�b�v�e���|�̋Ȃ����傱���傱����C���t�c�[�ɂȂ���������B���̕��C�ނ�̌��_�ł���Z�I�ʂł̐��ׂ̍����_�Ԍ����܂�����ǁC����͂܂��C�ґ�Ƃ������̂ł��傤�B���E�߂ł��B���������� |
 Thomas Rückert "Blue in Green" (Pirouet : PIT3020) Thomas Rückert "Blue in Green" (Pirouet : PIT3020)�@old devil moon �Asidran �Bperpetuum �Crainy day �Dhouse �EI should care �FDon Luigi �Gblue in green �Hon and on Thomas Rückert (p) Matthias Pichler (b) Jochen Rückert (ds) 2001�N�ɖ��������Ĕ��\���������[�_�[��w�f�r���[�x���C���̑����ꕔ�̍D���Ƃ̊ԂŘb����Ăg�}�X�E�����b�P���g�B1970�N�������c�u���N���܂�ł�����C�����V�l�̌��t�͎������܂��B�Ђƍ����B�W���Y�E��Ȋ������R���[�j�����y�@�o�g�Ƃ������Ƃ́C�ނ��܂��W�����E�e�C���[�̍���B�f�r���[���x�ꂽ�̂́C���̌�C�N���E���E�f���y�@�֓]���ă}�X�^�[�N���X�i�݁C2000�N�܂ŕ��𑱂��Ă�������̂悤�ł��B�f�r���[��C���[�E�R�j�b�c��A�_���E�i�X�o�E���C�W�����E�S�[���X�r�[��m���h�̊ԂŒ�������Ă����̂��C���̖L�x�ȋ��{�ɗ��ł�����Ă̂��Ƃł��傤�B�ꎞ�C���܂�b����Ȃ������悤�ȋC�����Ă��܂�������ǁC�{�l�͂������ă}�C�y�[�X�Ɋ����𑱂��Ă����l�q�B2004�N�ɂ́C�Z��q�̃q���[�x���g�E�k�b�X�Ɠ����s���G�b�g�ɈڐЂ��C�x�[�X���}�b�g�E�y���}���Ɋ������g���I�ő���w�_�X�g�E�I�u�E�_�E�g�x�\�B�{�Ղ͂���ɑ���2006�N�ՂŁC���C���n���g�E�~�b�R�̃��Y�����Ŗ����������S���S���E�x�[�X�̐V�s�}�e�B�A�X�E�s�b�N���[�ɍēx�C�x�[�X����ցB�����ɂ��R���[�j���y�d�炵���m���h�R���e���|�����[�E�W���Y������Ă܂��B�~�b�R����́w�����[�Y�x�Ȃǂɂ��ʂ���m�I�}���̗������^�b�`�ƁC�v���I�ŏ���L���ȃI���W�i���ȁC�Â������n������g���ꂽ�X�^���_�[�h���߂̃��`�G�́C�����ɂ��W�����E�e�C���[�B����܂��~�b�R���l�C�f�r���[�����ɔ�ׂĒm�I�}���������C���\�����v���I�ɂȂ�͂������̂́C�P������厖�ɂ����C�i�C�[���Ń����f�B�b�N�ȃt���[�W���O�ɁC�ނ炵���������������D�܂��������܂����B�̂ċȂȂ��o������ϗǂ��Ǝv���܂�����ǁC�ЂƂ~�������C�X�^���_�[�h�͏����M��߂��ł����B����������Ⴓ�����������Ă��܂��̂́C������Ɩܑ̂Ȃ��ł��˂��B�ł����S���Ē����܂��B�X���[���E�C�Y�E�r���[�e�B�t���ȃR���[�j���h�̏G��Ƃ��Ă��E�߂ł��B���������� |
 Bob Alberti "Nice N' Easy" (Dolphin : 6002) Bob Alberti "Nice N' Easy" (Dolphin : 6002)�@nice n' easy �Athe gentle rain �Ba beautiful friendship �Cspring will be a little late this year �Dsqueeze me �Ea nightengale sang in Berkeley Square �Fwonder why �Gmy foolish heart �Hthe heart of mine �Ithe touch of your lips �Jmy shining hour �KEmily Bob Alberti (p) Delbert Felix (b) Mark Husbands (ds) ���[�_�[��1934�N�u���b�N�������܂�B�T�㑱�����y��ƂŁC�e���A���x���e�B�y�c�Ȃ�A�}�I�P�������Ă������Ƃ�����C�t�H�[�g�E�n�~���g�����Z�ɐi��16�ɂ́C�ނ��܂��`���[���[�E�X�p�C���@�b�N�y�c�ɓ����đ������v�������J�n�B���̌�̓��X�E�u���E����C�E�v���}�y�c��n������C�O���j�b�W�E���B���b�W�����_�Ɋ��������悤�ł��B�������C�o�b�v�����̉��ł͕�����Ȃ�������ł��傤�B1960�N�ɂ�TV�ƊE�ŋ���Ă������Ƃ����ӂ��ă��X�ֈڏZ�B�|�[���E�A���J��W���j�[�E�}�e�B�X�C�p�e�B�E�y�C�W��̉��y�ēɂȂ�C1974�N����1983�N�ɂ̓W���j�[�E�J�[�\���́w�g�D�i�C�g�E�V���[�x�Ńs�A�m��e���ȂǁC�����ҋƈ꒼���B����Ȍ�m���܂��W���Y�ɉ�A�����̂́C1996�N�ɃJ���t�H���j�A�ɊJ�Ƃ����h���t�B���E�X�^�W�I�̉��y�R�[�f�B�l�[�^�[�A�C���W���Ă�l�q�BTV�ƊE�̓W���Y���t�Ƃ���قǖׂ������ł��傤����C���Ȃ薼�𐋂�������̗]���́C�I�X���K�Ș^�������ʼn߂������ƍl������ł��傤�B�ނ̃X�^�C���́C�A�����J�̕Гc�ɂɗǂ�����^�C�v�́C�����ŃG���K���g�ȃs�A�m�B�����f�B�A�X�Ő܂�ڐ������P���\���ƁC�e�f�B�E�E�B���\���`�W���[�W�E�V�A�����O���̎�̗ǂ��R�[�h�ł��B�J�N�e���Ƃ����Ă��Â����邳�Ƃ͈�����悷�C�����ƊO�A�݂̂Ȃ��J�N�e���E�s�A�m�ł��B�ŋ߂̐l�Ŏ����悤�ȃ^�C�v�������悤�Ɣ]���̋L�����܂�����ƁC�����Ă��閼�O�̓��C�E�P�l�f�B��o�[�g�E�_���g���C�W���b�N�E�u���E�����E�ȂǁC������̒n�����s�傪�����B����p�ŃN�Z���Ȃ��C���������Ό��������NJŔ��҂Ƃ��Ă͖ʔ����Ȃ������m��Ȃ��B�ނ͖{�^������O�N��C�n���[�E�A�����Ƒg��ŃJ���e�b�g�^�����o���Ă�͗l�B���y�����炷��ƁC�ނ��낱����̕��Ŗ{�̔������Ă����B�ꉞ�܂�HMV�ŗ��߂�悤�ł����C�ʂ����ē��ׂ���̂��B���������� |
 Metta Quintet "Subway Songs" (JazzReach-Sunnyside : SSC 1151) Metta Quintet "Subway Songs" (JazzReach-Sunnyside : SSC 1151)�@morning rush �Aunderground �Bsubway suite pt.1-3 �Cfast forward �Dunderground messenger �Eephemeral muse �Fevening rush Helen Sung (p) Marcus Strickland (ts, ss) Mark Gross (as) Joshua Ginsburg (b) Hans Schuman (ds) ���b�^�E�N�C���e�b�g�Ƃ����C1994�N�ɃW���Y�̕��y�����ړr�ɑn�݂��ꂽNPO�c�́w�W���Y���[�`�x�̖ڋʃv���W�F�N�g�Ƃ��Č������ꂽ�A���T���u���B2000�N�ɍ��ꂽ�f�r���[�Ձw�S�[�C���O�E�g�D�E�~�[�g�E�U�E�}���x�́C�����W���Y�E�V�[���̃g�b�v�𑖂��Ă����^�[�i�[�`���[�[���E�B���P�����j�ɂ����ϔ��q�R���e���|�����[�E�W���Y�ōD���Ƃ����삳��������ł����B6�N�U�����̖{�Ղ́C�n�ݎ҃n���X�E�V���[�}���ȊO�͑S�����B�}�[�N�E�O���X���͂��߁C�`���h���ۂ��ʁX�������C���������ς�����͗l�B�����h���̎����e�����e�[�}�ɒn���S���̌��ʉ����}�������R���Z�v�g�E�A���o���̑̂��Ƃ����{�Ղ́C�ǂ������������S�Ȏ嗬�h���[�_���E�n�[�h�o�b�v�֊����܂����B�ꌾ�Ō`�e����Ȃ�C�u���C�A���E�u���C�h�E�t�F���[�V�b�v�̃R���e���|�����[�l���ƁC�N���X�E�N���X�n�̝h�R�}���B�y�Ȓ҂ɃW�����E�J�E�n�[�h�C�}�C�����E�E�H���f��������A�ˁC�X�g���b�N�����h�C�W�~�[�E�O���[���ƃo�����X�����B�O���X�C�X�g���b�N�����h�̔S�������A���T���u���͐V�嗬�h���������f�i�����܂����C���Ԃ�ȃ��[�h�E�s�A�m��e���w�����E�X���͍�Ȃ��܂߂ăZ���X���ǂ��B�x�[�X�̃M���Y�u���N���n���Ȃ���V���A�ł��B����ȗǂ����ƂÂ��߂̖{�Ղ��C�Ȃ��������̂S���Ȃ̂��B�����Ȃ�ł���E�E�B���ɒv���I�Ȍ��׃K�A���m�f�X���E�E�B�p�\�q�ł����^�ł��邱�̌䎞���ɁC��̂ǂ������^����������炱���Ȃ�̂��B����Ɋ��x�ނ�m�C�Y�ƃN���b�N���m�C�Y�������B��E��b�����ʼn����Ѓ`�����l����������߂����肷��Ƃ���ɁC�p�`�p�`�������������C�����Ȃ��Ȃ�ċC���ł͂���܂���B�������S�҂ɓn���Ă���B�r���ŋC�Â��Ȃ��������ȁE�E�B���炭�C�J�Z�b�g�^��MTR�Ř^������Ȃ��ł����ˁB�f�W�^���@��ł͂܂�����Ȃ��m�C�Y�ł��B�w�b�h�����ՁE�ю����Ă�����ł��傤�B���吧��Ƃ͂������e��������E�E�B�������� |
 Joe Farrell "Skate Board Park" (Xanadu-Breaktime : BRJ-4547) Joe Farrell "Skate Board Park" (Xanadu-Breaktime : BRJ-4547)�@skate board park �Acliche romance �Bhigh wire �Cspeak low �Dyou go to my head �Ebara-bara Joe Farrell (ts) Chick Corea (p, ep) Bob Magnusson (b) Lawrence Marable (ds) 1986�N�ɁC48�̎Ⴓ�Őɂ������S���Ȃ����W���[�E�t�@�����B��ʂɂ̓`�b�N�E�R���A�Ɨ����^�[���E�g�D�E�t�H�[�G���@�[�iRTF�j�Œm�����m�ł��B�o���삪�ǃt���[�W�����Ȃ����C�����Ń\�v���m�E�T�b�N�X�ƃt���[�g�𐁂������߁C�ނ͂Ȃ��Ȃ����̃C���[�W���甲�����܂���ł����B��\��Ƃ��Ă����Ζ��O�̋�����w�A�E�g�o�b�N�x���n�߁CCTI����̘^���̓N���[�h�E�e�C���[�̍D�݂���݂����N���X�I�[���@�[�H���B���ۂɂ̓~���K�X�剺�ŁC�r�o�b�v��̃S���S���e�i�[�ł���Ȃ���C�o���ƈ����ւ���RTF��CTI�ɖ|�M���ꂽ�O�������C�ʂ����Ė{�l�ɂƂ��Ė{���ɍK�^�������̂��́C�r���S���Ȃ��ł��傤�B�l�I�Ȃ��b�ŋ��k�Ȃ���C���͎����t�@������m�����̂�RTF�ł͂Ȃ��C�w�o�[�h���o���b�Y�x�Ȃ�p�[�J�[�Ǔ����ՁB�X�^���E�J�E�G���̃s�A�m���]���C����������Y��f�i������Ԃ�Ԃ艹�Ő����܂���j�L���e�i�[�ɎQ�����̂����̌��B�ނ�����RTF���C���܂�̃M���b�v�ɂт����肵���N�`�ł������܂��B1979�N�Ƀ��[�i�[���烌�[�x�����ڐЂ��Ĕ��\�����{�ՂŁC�߂������������悤�ɃI�[�\�h�b�N�X�ȃW���Y�։�A�B����ȍ~�͖S���Ȃ�܂ł����Ǝ嗬�h�H���̍�i����葱���܂����B�I�X�Ɗy���C�ȃ������W�A���E�e�i�[���ɁC�J�ł͌�����������Ȃ�����ȍ~�̏���̂ق����C�ނ����肽�����Ƃ����ĔޓI�ɂ͍K����������Ȃ����Ǝv������B�����ނ��ŏ�����CRTF�����łS����Y�Ƃ��ăf�r���[���Ă�����C�����m���x�͗�����Ƃ��Ă��C�t�@���͐F�ዾ�Ȃ��ɂ��̏L���e�i�[���C�����ȕ]�������Ă��ꂽ��Ȃ��ł��傤���B�͂�����\���グ��B���B�ł��C�̏L���������̔M���e�i�[�ɖj�ɂމ���B���������m���Ă��ǂ���Ȃ��ł����˂��E�E�B�������� |
 Alex Riel Trio "What Happened?" (Cowbellmusic : #14) Alex Riel Trio "What Happened?" (Cowbellmusic : #14)�@yesterdays �Anature boy �B100 m spurt �Cwithout �DI'm getting sentimental over you �Eac-cent-tchu-ate the positive �Fgiant steps �Gdreaming streaming �H3rd dimension �IIdaho Alex Riel (ds) Heine Hansen (p) Jesper Lundgaard (b) 1940�N�R�y���n�[�Q�����܂�̃A���b�N�X�E���[���́C�P�j�[�E�h�����[��x���E�E�F�u�X�^�[��n���g�̑啨�Ƃ̋������o�Ĉ�ĂĂ���������B�W���Y�E�V�[���̑�ꐢ��B1965�N�ɂ͂��̃r���E�G���@���X�E�g���I�̈���ƂȂ�C���j�J�E�[�b�^�[�����h�̘e���ł߂ĉ��B�c�A�[�B���̌o���l�����ō�����ԈႢ�Ȃ��H���ɂ͍����ł��傤�B�ŋ߂͗I�X���K�̘^�������d�˂Ă���悤�ŁC�P�j�[�E���[�i�[�Ƃ͎�̊O���ӁB����ł͎��̓o�p�ɂ��O�����ŁC���R�u�E�J�[���]����I�����B�G�E�A���e���[�l����}���ċ���݂����^��������������Ă��܂��B����Ɉʒu�Â�����ł��낤�{�Ղ́C1978�N�O���i�A���܂�̎��n�C�l�E�n���Z�����}���C��䏊��l�ŋ���݂��B�s�A�m��2000�N�Ƀ��g�~�b�N���y�@�ɓ��w���C���Ƃ����̂�2004�N�������Ȃ̂ŁC�{�Ղ͍݊w���̘^�����������ƂɂȂ�܂��B��قNJ��҂���Ă����ł��傤�B���ہC�^�������łɃW���j�[�E�O���t�B����n�[�u�E�Q���[�C�t�B���E�E�b�Y��n���g��䏊�Ƃ̋��������ւ�ނ́C�o���L�x�B�}�����̇@�ł����݂Ȃ��w������Ă��āC�Ȃ�قNjZ�p���m���B���̌���ĉ����Ă�Ƃ�����݂�ƁC��䏊�������ނ����C�ɏ������̂ł��傤�B�����Ȃ��C���Ɛ\���܂����C���̐l�̃s�A�m���ǂ����G���ɕ������Ă��܂��B����̃V���v���ȏ[�ĂƉE��̒P�������������J�T�J�T�n�̃X�^�C���ŁC�Ō����ׂ��d���B���̂��߁C�ǂ����Ă����t���p���p�����Ə㊊�肵�C���s�����R�����Ȃ��Ă��܂��B���̂����C���y���͕ێ�I�Ńo�s�b�V���Ȃ�����C�������艉�t���������ɂȂ��Ă��܂��C�Ԃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B�����ĉ̐S���Ȃ��킯�ł��C�e�N���Ȃ��킯�ł��Ȃ��̂ŁC�v�͑Ō��̍D�݂Ȃ�ł��傤�B�ł��C���������s�A�j�X�g���ƁC�����E�����O�����͂ق�Ƃɐ����e����ȂȂƁC���݂��ݍĔF���������Ă��܂��܂��B�������� |
 Steve Kuhn, Steve Swallow "Two by Two" (Owl : SSC 3526) Steve Kuhn, Steve Swallow "Two by Two" (Owl : SSC 3526)�@gentle thoughts �Atwo by two �Bremember �Cwrong together �Deiderdown �Elullaby �Fladies in Mercedes �Gdeep tango �Hpoem for #15 �IMr.calypso Kuhn �JEmmanuel Steve Kuhn (p) Steve Swallow (b) �T�[�W�E�`�����t�̂��ꂳ��}�[�K���b�g�Ɏ�قǂ����C���q�Ɍق��ăv�����肵�Ă���C�͂┼���I�B���������G�X�ƘV�������L���[�����B1967�N���琔�N�ԁC�X�g�b�N�z�����ɋ����\���CMPS��ECM�Ȃǘ^���̗D�G�ȉ��B���[�x������ɐ������݂����āC������O��m����悤�ɂȂ�܂����B�Ђƍ��͉��B�C���[�W�������Ă��C�ފ݂̃��[�x���̘^�����ς�����Ǝ~�߂��������������悤�ł����ǁC1990�N��ɓ���ƒB�ς����̂��^���ĊJ�B���̍��ɂ́C�ŋ����C�����Ղ�̃��o�[�g�⍶��̃|�����Y���b�N�Ȉ��Ăɓ����Â�����C�G�X�ƘV�Ԃȃs�A�j�Y���ɓ��B�B1995�N�ɐ������܂ꂽ�{�Ղ́C���ăG���L�x�[�X�ւ̂������������Ă��a���ɂȂ������F�X�����E�ƁC�]�l�����܂ʓ�d�t�B�W�肪�����Ƃ���C��l�̎���Ȃ��C�ӂ���ʼn��t�������̃f���I�^���ł��B����ECM���ʂ���������ȗ͂�����l�̃I���W�i�����C�����҂̎�Œ�����Ƃ����̂͑傢�ɖ��͓I�ŁC�����w���B�m���Ƀ����J���ł��ǂ��Ȃ��l���̊y�Ȃ͂ǂ���������C���߂ė��҂̍˔\�Ɋ��Q���܂����B�ɂ�������炸�C���㊴�ɂ͂ǂ�������߂Ȃ����̂��c���Ă��܂��B���Ă͍d���_�o���Ȍ����L���L���ƑΛ������͂��̎���Ȃ������C����d�˂���l�͋ɂ߂ĉ����ɍČ��O���Ă����B�ǂ��ƂȂ��吳�Ղ��ۂ����F�ŋ����߂�U���u�Ԃ�����X�����E�̃G���L�x�[�X�ƁC�G�X�Ƃ����L���[���̃s�A�j�Y���B�x�N�g����ꡂ��ɊJ���Ă���͂��B���ꂪ�v���̂ق����̕ϓN���Ȃ��W�X�Ɨ��݁C��Ɏ����I�ȏ���҂��`�Â����Ă����B�����͌����Ĉ����Ȃ��̂ɁC�Ȃ�����a�����o���Ă��܂��̂́C�e�X���[���Ƃ���őΘb�̑���������C�ۂ���ꂽ�����ɓO���Ă��邹���Ȃ̂ł́E�E�����l����̂͐��������ł��傤���˂��B�������� |
| Other Discs |
 Achim Kaufmann "Kyrill" (Pirouet : PIT3020) Achim Kaufmann "Kyrill" (Pirouet : PIT3020)�@linjanje �Aslow roundabout �Bensormasque �CDewey Redman �DMisha Antlers �Escarine �Fimbo �Gdorobo �Hblue-brailled �IStanley park Achim Kaufmann (p) Vardi Kolli (b) Jim Black (ds) �k�b�X�����āC�����b�P���g�����āC��������R���[�j���y�d�̓������Ɖ����Ă���C�����Ȃ��ł��Ȃ��ŋ߂̃s���G�b�g�E���[�x���B�{�Ђ̓~�����w���ŁC�R���[�j���Ƃ͊W�Ȃ��C�������ł����C�����l�I�Ȍq����ł������ł��傤���B1996�N�ł������C�o���g�[�N�����������w���B�[���x�őN��Ȉ�ۂ��c�����A�q�[���E�J�E�t�}�����C�C���t�����̊Ԃɂ��s���G�b�g�ɐЂ�u���C�R���X�^���g�ɍ�i����𑱂��Ă���悤�ŁB2008�N�ɏo���g���I��̖{�Ղ́C�S�Ȃ�����B�C������Έ�ڗđR�Ȃ悤�ɁC���̌�̔ނ͎v���I�ȃt���[�E�W���Y�̕����ɑǂ�����悤�ł��B�i�^�̂悤�ɃS�����Ƃ����d���ꖡ�̑Ō��ɁC�|�S�n�̘a����D������ĕ����Ɍ��s�A�j�Y���́C������Ȃ��J�E�t�}���̂���B�����N�ƃo���g�[�N�̊Ԃɐ���������e���C�K�v�ŏ����̍\�������a�݂�^���Ȃ���C���Ȃ��t���[�E�W���Y�����t�B�Ǖ��ɂ��ď����̃��Y���������x���͗ǍD�ŁC���x���̍����������邱�Ƃɐ������Ă���Ǝv���܂��B�����̂��ْ̂͋��������C���Ă̑N��ȁw���B�[���x�̕З͏[���ɉM����B�ƂȂ�܂��ƁC��͂����t���[�E�W���Y�I�ȉ��y�����D�����ǂ����̈�_�ɐs���܂��傤�B�L�[�X���G���ɂȂ����悤�ȃt���[�Y�Ƙa���C�h�b�^���K�V���[���ƒǔ����鑾�ۂ̃p���X���C���킹��̂��h�����ȃx�[�X�Ɗ�ɗ��ݍ����đ������̉����E���u�I�I�b�C�ْ��������`�I���ꂼ�t���[�I�v�ƗL���q������̂��C����Ƃ��u���������₾�C���N�K�L���݂Ă�E�E�v�Ǝv���Ă��܂��̂��ŁC�]���͑傫������܂��傤�B�����N�ƃo���g�[�N�Ɉˋ����C���Ղȏ������恂���d�h�ȉ��y���ł��邱�Ƃ͏[���ɔF�߂��C��������A���o���ꖇ�Ă��肳�ꂽCD��������Ă����܂�������Ȃ��������́C�����ʂ��̂��h���h���b�v�E�A�E�g�B�܂��D���ȕ��͑����Ɋy����ł��������B�A�������B�������� |
 Paolo Birro Trio "Live at Siena Jazz" (Splasc(h) : CDH 524.2) Paolo Birro Trio "Live at Siena Jazz" (Splasc(h) : CDH 524.2)�@I'm getting sentimental over you �Astablemates �Balcool �Clament �Dyou do something to me �EI got it bad �Flittle Willie leaps Paolo Birro (p) Aldo Zunino (b) Alfred Kramer (ds) �������������C�w�t�F�A�E�v���C�x�͂܂��ꓖ���肾�ƔF�߂Ă��܂������������C������p�I���E�r�b���B2000�N�ɏo���g���I�Ղł��B1962�N�m���F���^�ɐ��܂�C���X�̓N���V�b�N�̉��t�Ƃ�ڎw���C���B�`�F���^���y�@�ɐi��ŃJ�����E�}�c�H�[���Ɏt�����C1987�N�Ɋw�ʂđ��ƁB�������C���̍��ɂ̓W���Y�̕����ʔ����Ȃ��ē]���B���[�E�R�j�b�c��X�R�b�g�E�n�~���g���C�X�e�B�[�u�E�O���X�}���̘e���ł߂Ė��������܂����B�\���֓]�����̂�1992�N�C�}�E���E�l�O���C�T���h���E�W�x���[�j�Ƒg�h�������X�E�g���I����B�w�t�@�j�[�E�����x�͏����ȉ���ł��������B�ނ̖������߂��̂͑���1995�N�ɔ��\�����g���I��w�t�F�A�E�v���C�x�B���N���Ղ��C���W�J�E�W���Y����̔�]�Ɠ��[�ŁC�ŗD�G�܂���܂��Ă���̂��Ƃł����B���̂܂܃g���I���p�����Ă�����C����ɑf���炵�����ʂ�������ꂽ�ł��傤�ɁB�Ǘ~�Ȕނ͂Ȃ����e���ҋƂ��p���B���Ƀg���I�Ŋ猩���������̂́C�ܔN���o�߂����{�Ղł����B�ނ͂��̃g���I�͂������藈���̂��C������G��ł܂��ܔN��ɂ��w�X�v�����O�E�W���Y�E�g���I�x�𐧍삵�܂��B���炭�������ł̓��r�����[�E�g���I�Ƃ��Ċ������Ă�̂ł��傤�B�ނ��ǂ����Ă��̃g���I�ł̊������p������̂��C���������ėǂ�������܂���B�������ɉ����g���Ă����N�����[���݂̓����ۂ́C�r�b���̃s�A�m�̏c�̉A�e���Y��ɎE���Ă��܂��܂����C�Y�j�[�m�̃x�[�X�͌������Ⴂ�����ʼn��̐c�������Ă���B2005�N�ՂŊ������s�����C���ǖ{�ՂōĊm�F���邱�ƂɂȂ�܂����B���y�Ƃ������鋏�S�n�̗ǂ����C�K�������������ʂ������錋�ʂɂ͌q����Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�˂��B�������� |
 Tom Cohen "Diggin' In - Digging Out" (Double-Time : DTRCD-150) Tom Cohen "Diggin' In - Digging Out" (Double-Time : DTRCD-150)�@solar �Asoftly as in a morning sunrise �Banthropology �CChagall �Dthe cat �Edesert flower �Fwell, you needn't �Gnot even a hat �Htruth is stranger than fiction Tom Cohen (ds) Chris Potter (ts) Peter Madsen (p) Peter Herbert (b) �j���[�A�[�N�o�g�C�t�B���f���t�B�A�����_�Ɋ�������g���E�R�[�G���́C���Z�݊w����1971�N����W���[�W�E���V���g����w���Ƃ�1975�N�܂ŁC�g�j�[�E�E�C���A���X�Ɋw�h���}�[�B�t������̃��K�[�g�̗���������ȃV���o���E���[�N��ɂ��������͈͂͋ɂ߂čL���C�t�B���f���t�B�A�Ɉڂ��Ă���̓t���[�W�����E�O���[�v�y�J�^���X�g�z��u���W�����y�́y�~�i�X�z�ɍݐЂ�����ƁC�t���[�����X�Ƃ��Ă��Ȃ莩�R�Ɋ������Ă���悤�ł��B�����ނ�F�m�����̂́C1997�N�ɔ��\���������[�_�[��w�g���E�R�[�G���E�g���I�x���Ă���ł������C�����͐��������Ă��܂��ۂɂ͎c�炸�C�ނ���s�A�m��e�������E�g�[�}�X�̃��[�h�E�s�A�m�ɖڂ�D���Ă���܂����B�{�Ղ͂��ꂩ��Q�N��ɐ������܂ꂽ���[�_�[����ŁC�����͂܂����{�ł��قƂ�ǒm���x�̂Ȃ��������s�[�^�[�����Y�����Ɍ}���C�N���X�E�|�^�[�𗧂Ă��J���e�b�g�Ґ��B�l�I�ЂƂƂ��Ă��C�ނ��Ȃ��Ȃ��̖ڗ����ƕ����낤�Ƃ������̂ł��B�r���[�r���[�ƃN�Z�̂��鉹�F�̃|�^�[�ɁC�E�C���g���E�P���[�͏��F���̎p�Ȃӂ���̃s�[�^�[�B��荇�킹�Ƃ��Ă͂��Ȃ����C���ہC�C���E�e���|�ɂ͑���Ȃ�����C���Ȃ�t���[�ɉ��t����Ă���B���Ƀ}�h�Z���́w�X���[�E�I�u�E�A�E�J�C���h�x�����Ƃ͎v���Ȃ��قǁC�t���[�ȃ��[�h�E�s�A�m�ő�\��B�ǐ����鑾�ۂƍ��킹�āC�O�삪�R�̂悤�ȍ�i�ɂȂ��Ă܂��B�C�G�ɑ}�����ꂽ���ɂ��������o���[�h���n�߁C�}�h�Z���̒Ȃ͂ǂ���ǂ������Ă���C���x�߂Ƃ��ė��������܂����C�R�[�G���̃��K�[�g�t�Ƃ��Ă̒B�҂����ǂ�������_�ł́C�{�Ղ͑O���肸���Ƃ��E�ߓx�������B�������C�}�h�Z���̃��@�[�T�C�^�����̓x�N�g���̊J����傫�����Ă��܂��C�ǂ��ɂ���i�ɓ��ꊴ������܂��C�X�^���_�[�h�Ȃ̉��t�̓t���[�ȑf�`���݂Ē����̂��h���B��肢�͔̂F�߂���������C�ɂ͂Ȃꂻ��������܂���ł����B�������� |
 Enrico Pieranunzi, Enzo Pietropaoli, Roberto Gatto "Moon Pie"
(YVP-Devox : CDX 48803) Enrico Pieranunzi, Enzo Pietropaoli, Roberto Gatto "Moon Pie"
(YVP-Devox : CDX 48803)�@today �Aoccasions �Bmartina �Cskies �Dbefore the wind �EI'm looking for you �Fno exchanges �Gautobahn �Huptown style �Iafter the rain �Jblue and golden �Kspeedy girl Enrico Pieranunzi (p, key) Enzo Pietropaoli (eb, g) Roberto Gatto (ds) �n���֏o������Ƃ��̂������̈�Ԃ̊y���݂́C����̒��ÔՉ��ɑ��𗯂߁C�|�����߂ɕ���CD�Q��ʂ��āC���̒��ɏZ�ސl�X�̖��x�𐄂��ʂ邱�Ƃł��āB�ꐔ��Ŋ���Ă���ƁC����ɂ��̒��̉��y�I���{�݂����Ȃ��̂��C�I��ʂ��ē����Č�����悤�ɂȂ�B��ꂽ�n���s�s�̃u�N�I�t�ɃG�����R�́C�������ʓI�ȃX�g���C�N�]�[�����炱�����O�ꂽCD������ł���̂�����ƁC���w���҂̐l�ƂȂ肪�Â�C���ꂾ���ʼn���瓾�����C���ɂȂ��Ă��܂��܂��B1987�N�C���̃X�y�[�X�E�W���Y�E�g���I�����̃G�����R���C����Ȏ�C�̎���ȃA���o��������Ă����Ƃ́C�����S���m��܂���ł����B1983�N�ɓo�ꂵ�C�ꐢ���r�������}�n�̃L�[�{�[�hDX-7�B�G���s������y�ɏo���C�j�i��16�����������B����ȍŐ�[�̊y�킪24���Ŕ�����B�o�������͐�������I�������̂ł��BDX-7�̕]�����ǂ����Ŏ��ɂ����ނ������ÁX����o���C�����̗���ɑ傢�ɋ����������Ƃ��Ă��ӂ߂��Ȃ��ł��傤�B�������Ė{�Ƃ̕Ў�ԁC�I�g�i�̊ߋ�ŗV�ԎO�l�̎p���C�v�����Ⴂ��YVP�̃J�^���O�ɍڂ��Ă��܂��܂����B�M������E�E�B���������Ƃ����v���Ȃ��i�j�B�L�[�{�[�h�̏h���͉��F�̕����B�s�A�m�e�����肷���тŗV�����ڂ̃A�����W�E�Z���X���C�`�[�v�ȉ��F�ɏ���Ĉ��������ɑ�����ʂ������C�A�}�`���A�L�����ځB�G���]�ɂ��]�|�̃M�^�[�����Ȃ��Ȃ������������肷���ł����ǁC���y���̂��̂��D�������U���B�k���E�V���W�P�[�g���B�ꉞ�͐^�����ȃt���[�W�����ł����C�����܂ō�����i�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�������C�G�����R�ł���K�R�����F���Ȃ̂͐\���܂ł��Ȃ��B�{�Ղ��u���ʍ�v�Ƃ܂ō��]����T�C�g�����܂�������ǁC���炭�C�G�����R�̃A���o���Ƃ��Ē������炱���̕��肾�����̂ł��傤�B������ |
 Joel Zelnik Trio "Move" (Felicia : THCD-118) Joel Zelnik Trio "Move" (Felicia : THCD-118)�@move �Awalk right in �Ba minor thought �Cblues web �Dtune up �Emaybe september �Fwill you be mine �Gcultivation Joel Zelnik (p) Harold Slapin (b) Dave Rose (ds) �n����w�ŃW�����E�~�[�K���Ɏt�����C�݊w����1967�N�C23�ɂ��Ă��̗L���ȃ��B���b�W�E�Q�C�g�Ɉ�x�o���B���̗]��������ė��N�C�{�Ղ����吧��B����ȊO�C�w�ǂȁ`���������̃g���I�C���̗��ʂ̏��Ȃ�����C���Ă̓}�j�A�����̊Ղ����������ȁB����ȃA���o�����߂ł��������B�}�j�A�̒��d����u���Ձv���ǂ�ȉ����C�����ÁX�w�����܂����B�꒮������ۂ́C�u�Ȃ�قǁE�E�w���̉��t���ȁv�ł��傤���B���[�_�[�͂����ɂ����l�A�}�`���A�E�s�A�m�e���B�a���@��t�@�̓f�C�u�E�u���[�x�b�N�ɁC�^�b�`�̃L�c���̓��W���[�E�P���E�F�C�ɗǂ����Ă���B����ȂɗL����قǗǂ����Ȃ��H�Ǝv�킴��܂���ł����B�܂��C�s�A�m�����ۂ��Z��B���ȉ��B���Y�����������B�u���[�x�b�N����̃u���b�N�E�R�[�h����ł��Ō떂�����܂����ǁC�^�w�̐ق���A�h���u�̂����Ȃ��͉B���悤������܂���B�S���S�������^���Ńx�[�X���ǂ���̂ƁC���A�ՂƂ��Ă̊��l�ƂŁC�喇�͂������}�j�A�̎��ɂ͑����Ȍ�����p���N���Ă��Ȃ��ł��傤���i���Ղ��I�������̂��́I�Ƃ�����тŖڂ��܂��Ă���Ƃ�������j�B�����g�K�����F2000�~���傢�̂������ɓ�����p���N���悤�����Ȃ��C�]�����߂���̂́u���l�͗�����Ȃ����v�̃��t���C���B�ƂĂ�20���߂��o���悤�ȃA���o���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B���Ȃ݂ɔނ͎��吧��Ŗ{�Ղ\��������̖ڂ����邱�Ƃ͂Ȃ��C�ǂ���猘�C�̐��E�ɖ߂���������悤�ł����C�z�[���B�E�g�����B���E�g���I�̃s�A�m�e���Ƃ��č��������B������ɂ��ăW���Y�̎�̃t�����V�[�k�E�G���@���X����ƕv���w���C�j���[�W���[�W�[�����_�ɉ��t�����𑱂��Ă���悤�ł��B�������� |
 Regina "Curiosity" (Atlantic : 32XD-534) Regina "Curiosity" (Atlantic : 32XD-534)�@sentimental love �Abeat of love �Bsay goodbye �Cbaby love �Dhead on �Elove time �Fbring me all your love �Gcuriosity �Hjust like you Regina Richards (vo) Leslie Ming (ds, e-perc, sqc) Gary Corbett (key, sqc, synth) Stephen Bray (key, rthm) Ira Siegel (g) Peter Zagare (b) Jeff Smith, Wayne Cobham, Najee Rasheed, Roger Byam, David Sanborn (sax) Rick Stevens, Leroy Evans (key, synth) et al. ���{�ꂾ�����Ǝv���Ă����ꔭ���iOne hit wonder�j�̊T�O���C�p��ɂ����݂��邱�Ƃ�m�����͍̂ݕĒ��B����������Ă��ꂽ�ނƈꔭ���̘b��Ő���オ��������ł������C�������̔ނ��F�m���Ă��Ȃ������ꔭ�����{�Ղ̎�l�����W�[�i���j�B1986�N�ɂ�������x�C�w�x�C�r�[�E�����x��S��10�ʂɑ��荞������C��x�ƞw����ɏオ��Ȃ������ꔭ���̊ӂł��B�u���b�N�����ɃC�^���A�n�ږ��̎q�Ƃ��Đ��܂�C�����[�}�E���g�E�}���n�b�^���E�J���b�W�����ȂցB1979�N�̑��ƌ�́C�p���N��j���[�E�F�C���̉��y�V�[���ɐg�𓊂��܂����B���N�CA&M�Ɍق��ăV���O�����Q���o���Ă���C�ӊO�ɂۂ��Əo�ł͂���܂���B�������ċ@����M���ޏ��ɖK�ꂽ��ڈ���̋@��C1986�N�ɏo���{�Ղ̃I�t�@�[�B���͓����C1984�N�́w���C�N�E�A�E���@�[�W���x�Ŏ��̐l�ƂȂ����}�h���i���C���傤�ǐV��̏������ł��āB�u���[���������X�e�t�F���E�u���C�̇C���C�}�h���i�͑ʖڏo���B���ʇC�̓��W�[�i�̐V��֓]�p����C�ޏ��B��̃q�b�g�ȂɂȂ�܂����B�u���C�������l���ćC�������C�}�h���i���Ȃ��{�c�ɂ����̂����꒮�đR�B����ł��ǂ����琬�����������W�[�i���𓊂��C�x�C�r�[�ȗ����̂��đ��̊Ԃ̐�������ɂ����B���̊Ԃ̗��s�ɔw�������C���̃X�e�[�W��ڎw�����}�h���i�́C�u���͂����x�C�r�[����Ȃ��B�q���͑낳�Ȃ����v�Ɛ���Ń_���E�u�����h����E�p�B�X�[�p�[�X�^�[�ֈ���O�i�����B�C���߂����Č�������l���͗l���C�ł��̂Ă�ꂽ�~�Ղ�250�~�ƈ����ւ��Ɍ��̂ł��B���� |
 Hilton Ruiz "Piano Man" (SteepleChase : VACZ-1094) Hilton Ruiz "Piano Man" (SteepleChase : VACZ-1094)�@one for Hakim �Amisty thursday �Bmedi II �Cstraight street �Dbig foot �Earrival �Fgiant steps Hilton Ruiz (p) Buster Williams (b) Billy Higgins (ds) 2006�N5��19���C�j���[�I�����Y�̃o�[�{���E�X�g���[�g�ō�����Ԃ̂܂ܔ�������C�ӎ����߂�ʂ܂�20����ɖS���Ȃ����q���g���E���C�X�B54�Ƃ܂�������ԍ炩����ꂻ���ȔN����������Ɏc�O�ł����B�����[�E���[�E�E�B���A���X�Ɏt�����Ęa���@���C�������ނ́C�X�g���^�E�C�[�X�g�l����ʂ��ăt�����N�E�t�H�X�^�[�̃r�b�O�E�o���h�ցB�v�G���g���R�ږ��̌������C�A�t���E�L���[�o���F���o�b�v�E�W���Y�ƍI�݂Ƀu�����h����X�^�C���̓��[�����h�E�J�[�N�̖ڂɗ��܂�C1974�N����1977�N�܂ŃJ�[�N�̃T�C�h�����߂ē��p��\���܂����B�{�Ղ͂��傤�ǔނ��J�[�N�̃O���[�v�ɂ���1975�N�ɐ������܂ꂽ�����[�_�[��B��䏊�o�X�^�[�E�E�C���A���X�ƃr���[�E�q�M���Y�̃o�b�N�A�b�v���̂����͂��B�T���o���̇@�ɋ���Ȏ������������̂́C����ȍ~�͂������ăI�[�\�h�b�N�X�ȃo�b�v�E�X�^�C���ł̉��t�B�������A�b�v�E�e���|�̇F�ӂ�ɂȂ�Ɛh�����ł����C�S�̂ɍr���ȉ��t�ł͂����ł����ǁC�t���[�W���O�͂悭�̂��C�Ȃ�قNJ��҂̐V�l���������Ƃ��ǂ�������܂��B���̌�C�ނ͉̔��̐��E�ŕ]������C�x�e�B�E�J�[�^�[��A�r�[�E�����J�[���̘e�ł������B�������C�ǂ��炩�Ƃ����ƃ��e���E�t���[�W�������Ő������Ă��܂��C�A�R�[�X�e�B�b�N�ȃW���Y���t����͋�����u���Ă��܂��܂����B�Ⴓ�̎c��{�Ղ��C�������ă��C�X�̑�\��Ƃ��čĔ������̂��C�{�Ղ��ނ̃W���Y���t�ƂƂ��Ă̎���������������Ƒ����Ă��邩��ł��傤�B�l�I�ɂ́C�����f�B�b�N�ȃ|�X�g�E�o�b�v���̇C�C�N���t�E�W���[�_���w�O���X�E�r�[�h�E�Q�[���Y�x�ӂ�ɓ����Ă����ȃ~�f�B�A���E�e���|�̇E�ӂ�Ɏ������������ł��B�������� |
�E�e�F2009�N12��24�� 4:48:39
|
��������䖳�������Ă��܂��܂����B �܂��ƂɜΜ��Ɋ����܂���E�E�B ����ɓ����̔@�����Ԃ������߂��̂��C���͐̂��Ȃ��E�E�B
�C�u�ł��ȁB�N���X�}�X�B �j�������C�����͕�����C�������E�E  �� �g�@�� ��  �����̃��o�j���ٓ��� �����[�N���X�}�X�̃V�[���\��̂����͎~�߂Ă���B
������x��ł���Ԃ� ���̒��͐����ς���Ă��܂��܂����ȁB �E�ł��Ȃ��瑝�����鑍���� �ō��ٔ������@����b�� ������v����錾�����s�v�S����b �C���T�C�_�[�������o�Y�� ���ꂾ���l�^�Ɏ������Ȃ����t�͏��߂Ă���Ȃ����낤���B ����ł��x�����T�����L�[�v�B�Ȃ��ȂB  ���āC�C�u�ł��ȁE�E�B �����͂����̔@���C����c��� �X�e�[�L�����C�P�[�L�� �̂Ēl�Ŕ����@���C�ܖڂ̓X��̌��� �D�����ԕ����邱�Ƃɂ��܂��傤�B�A�������B ���N�͐F�X�����āC�قƂ�ǍX�V�ł��܂���ł����E�E�B ���N�͂ǂ����낤�E�E�B�܂��܂��Z�����Ȃ肻�����Ȃ��E�E �\�߁C���߂�Ȃ����B |
||||
| ����ł͂܂������܂ŁC�����䂤��������B �����[�N���X�}�X�C�D�����N���B |
||||
| �Ձ`���h���@ |

����20�_�C����10�_�Ō��Ă�������
| SEO | [PR] ����!�����u���O �����z�[���y�[�W�J�� �������C�u���� | ||
